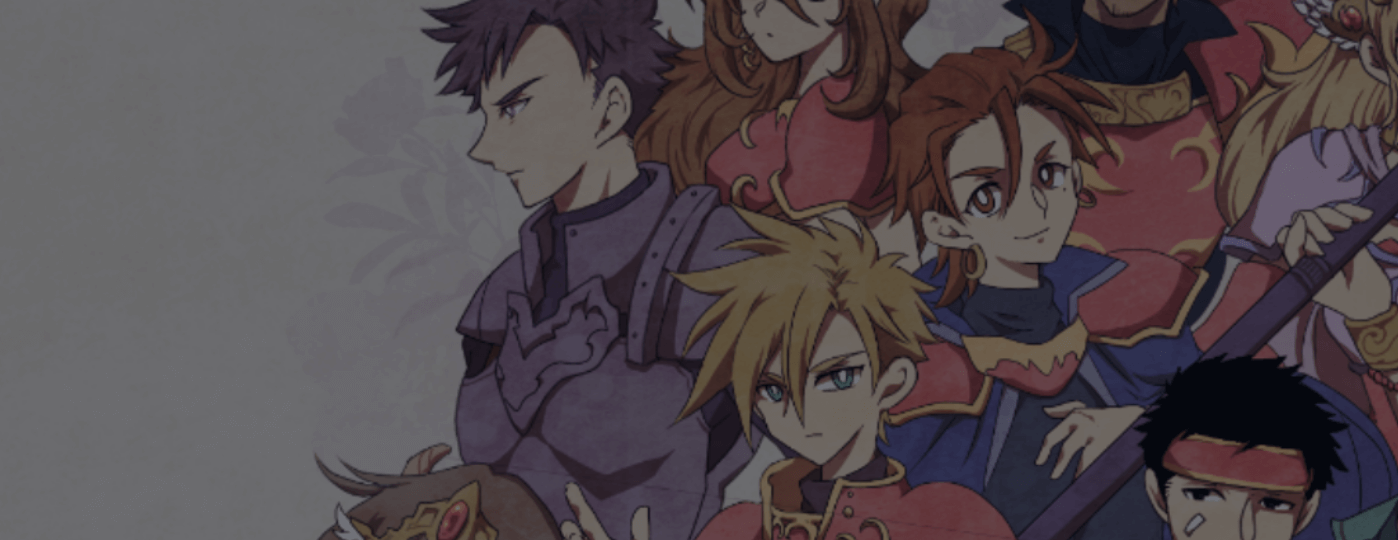1.竜胆色の瞳
- aAあ
- aAあ
- 横書き
- 縦書き
通された部屋には、僕を除いて五人の少年がいた。シスターに呼び集められた彼らは、僕を品定めするように眺めたり、あからさまにバカにした顔で見下したり、こちらに一瞥すらくれなかったり、様々だ。
ただ一様に、友好の意思がないことだけは明らかだった。僕の背中に放たれた、みんなのことは兄弟だと思っていいんですよ、というシスターの言葉は、ひどく場違いなものだとわかった。
シスターはゆっくりと、大業そうに口を開いた。
この子はココット。ここにいらしたのは神の思し召しです。今日からはみんな家族なんですから、彼のことは弟だと思って、色々と教えてあげてくださいね。
聖職者というのは、どうしてこんなに身の毛もよだつような胡散臭い話し方をするのだろう。歯の浮くようなシスターの紹介に、僕は気恥ずかしさを感じていた。
ここにいた子供達はみんな偏屈そうだったから誰も返事をしないと思いきや、彼らは途端に笑顔になって、僕を迎え入れた。
名乗り、親交の言葉を口にして、手を差し出してくる。もちろんそれは、舞台俳優が見たら卒倒してしまいそうなとんでもない演技だ。彼らみんな、安物のフレンドシップの奥に、軽薄で邪な笑みをたたえていた。
シスターは浅薄な親睦の様子にたいそう満足したようで、ここでの生活のことはお兄さん達に聞くといいわ、と言って上機嫌に部屋を出ていった。
シスターの軽い足音が、カツン、カツン、と、カウントダウンのように遠ざかっていく。
聖堂へ続く重い扉が、木のうなり声をあげて大きく開かれ、やがて閉じられた。
その音が響くと同時に、大人の視線から解放された彼らの態度は一変した。
動いたのは、アルゴスと名乗った少年だ。
アルゴスは体が大きくて、いかにも不良少年のボスといった、イヤになる程お決まりの風体だった。意地の悪そうな顔をして、にじり寄ってくる。
まさかハグでもしてくるわけではないだろうから、そうとなれば今僕の身に降りかかろうとしているのは危険。はたまたカタストロフィなのだ。
とっさに後ずさろうとしたけれど、アルゴスの取り巻きに回り込まれ、僕の退路は失われた。
アルゴスは胡散臭い笑顔で僕の肩をポンポンと叩いた後、敵意むき出しの顔に豹変して乱暴に胸ぐらを掴んだ。
「歓迎するよ。ココットちゃん」
アルゴスは僕の耳元で、ねっとりとつぶやいた。
生暖かな、卑しい吐息が僕の鼓膜に張り付いて、ゾッと鳥肌が立つ。
そして次の瞬間、僕の体を思い切り突き飛ばした。
僕の体は木の壁に叩きつけられて、凄まじい音をあげた。けれども、とっさに受け身をとったことで痛みはさほどなかった。というより、突然さらけ出された、露骨で、悪意たっぷりの暴力を食らったことへの驚きが何よりも大きくて、痛みや恐怖を感じるよりもはるかに呆然としてしまった。
「今までの坊ちゃん暮らしは、忘れるこったな」
さも悪そうに吐き捨ててみたものの、僕が痛がるそぶりも、怯えるそぶりもしないのが気に食わなかったようだ。アルゴスは汚らしく舌打ちをして、磨り減った靴の底をキュッキュと何度か床にこすりつける。
そして、にっこり笑うと同時に、僕の腹を思い切り蹴り上げた。
危ない。
と、思った時には、つま先が腹部にめり込んでいた。
息がつまる。視界が歪む。
今度は、効果てきめんだった。
膝をついてなるものか。グラつく体をなんとか支えようとする気持ちはあったけれど、無理だった。数歩よろめいたのちに、僕はついに地面へとへたり込んでしまった。
その様子が彼らにとっては、さも可笑しかったのか、取り巻きが甲高い声で笑い出す。アルゴス自身も、勝ち誇ったように息を荒くしていた。
痛みは、どんどん広がっていく。うずくまって、息もまだちゃんと出来ない僕を見て満足したのだろう、彼らは彼らなりの挨拶を口々にして部屋を出て行った。
また遊んでやるからな!とか、ママのところに帰った方がいいんじゃないか?とか、人を馬鹿にした言葉を吐き捨てられても、悔しさや憤りもなかった。
体の中でいっぱいになる痛み、ただそれだけが僕の全身を満たしていた。
彼らの品のないまばらな足音が、しだいに遠ざかっていくのがわかって、痛みの最中、僕はほんの少しだけ安堵した。
部屋の中が、シンと静まり返る。
しばらくすると、部屋の外の、そばに流れる川の水音とか、鳥の羽音だとか、乱暴に歩く誰かの足音なんかがかすかに聞こえてきて、街の雑踏とは違う自然の音ってこういうものなんだなぁ、と、痛みのすぐそばに変に冷静な気持ちを携えていた。
キシ。
と、すぐそばで、本当に近くで、何かの音がした。
それは板の、軋む音。明らかな、人の気配。
驚いて気配の方を見ると、まだ一人だけ少年が残っている。
見た目は、僕より頭ひとつくらい高いほどの背丈だろうか。
腕を組み、壁に体を預けて佇んでいる。窓からあたたかなピンク色の夕日が差し込み、顔や、髪の色は逆光でよく見えない。
けれど、影を宿したその顔は、冷徹に見下しているように僕には思えた。
思えば、先ほどの偽りの親睦の場でー人だけ名を名乗らず、輪の中に入ろうともしない少年がいた。それはもしや、彼ではなかったろうか。
彼は、僕と目があったからなのか、壁に預けていた体をゆっくりと起こした。そして、今まさに、歩み寄るようなそぶりをした。
ギョッとした。
冗談じゃない、と思った。
瞬時に、最悪の事態が頭に描かれる。たとえば、彼はあの中でもひときわ暴力を愛し、陵辱に恋する少年で、あんなおふざけ程度の暴行じゃ満足出来そうにないから二人きりになる機会をずっと伺っていたのだ。そして今。火遊びで喜ぶ子供達が去った今こそ、虚栄も自尊心も届かない純粋な暴力の時を告げにきたのではないだろうか。
瞬時にしてよくここまで行き過ぎた考えにたどり着くものだな。と、自分に対して変に冷静な感想すらよぎる。確かに考えすぎかもしれなかったけれど、もし僕がどんなに楽観的でも、さっきの今で、きっと介抱してくれるに違いない、とは、思えるはずもない。
逃げよう。
そう決心して、なんとか立ち上がろうとする。けれども、駄目だった。
体は、重い。
思うように動かない。
膝を立てることすら、床に着けた手を浮かすことすら。精一杯やっても、それでも駄目だ。
けれど、というか、だからこそなのか、彼は歩みを止めなかった。
ゆっくり、キシ、キシ、と迫ってくる足音とは逆に、僕が、ほんのわずかしか持ち合わせていなかった抵抗する気力は、だんだんとどこかに失せて行った。
足音は、止まる。
こうべを垂れていた僕の視界に、ボロボロに擦り切れた革靴が映り込んできた時には、もう諦めの感情しかなかった。
ギィ、と、木の床がひときわ大きく軋み、彼はしゃがみこむ。
彼の顔が近付くにつれて、これから行われる暴虐への想像が鮮明になっていく。
恐ろしくて、僕は頭を抱え、固く目を閉じた。
肩にそっと手を置かれた時、体がビクッと痙攣するのを抑えられなかった。
「大丈夫か?」
彼の声を初めて耳にした、その時の気持ちは、なんというのか形容しがたい、どうしようもない気持ちだった。例えるなら、芽吹きを見守る時のような、春の日差しを受けた時のような、凍える体に染み渡るスープを頂く時のような、そんなものだ。
彼の第一声は、予想だにしてなかった善意の言葉だった。
想像とは真反対のことが起きて、突然火矢のように体を射抜いてきた善意に、僕は困惑した。彼の顔を見上げることもできなかった。
まさか気遣うふりをして、油断したところを嬲る趣味があるのだろうか、とすら思った。
ゆっくり、彼の顔を見上げようとした時、逆に彼が僕の顔を覗き込んできた。しびれを切らしたような、やや乱暴な声で、おい、と言って肩を揺すられた。
その時初めて、切れ長の、するどくてまっすぐな目を持った彼の顔がよく見えた。
灰がかった紫の、寂しい色をした瞳。
その瞳は一寸たりとも揺らぐことなく僕を見据えている。
そうしてようやく、僕は理解した。
ああ、彼は、僕を心配してくれていたのだ。
彼はまだ僕と同じくらいの年齢に見えたけれど、かすれてザラザラした声や、落ち着いた熱のない眼差しや、長い手足を持っていて、とても大人びていた。
問いかけに対して僕が首を縦に何度かふると、彼は頷いた。
「たった一発腹に食らっただけだ。なんともない、起きあがれる」
そう言って立ち上がり、ゆっくりと僕の手を引く。
さっきまであんなにも重くて膝も立てられなかった体が、彼の手に引かれて魔法のように軽く弾み、僕の両足はようやく尊厳を取り戻すことが出来た。
それでもやっぱり、蹴られた腹部はじんじんと熱いけれど、呼吸を整えていくにつれて落ち着いていった。彼の言う通り、大したことがなかった。
「な。アルゴスは脚が短い」
彼は途端にそう呟いた。
確かに目の前の彼の脚は長くてスラッとしていて、彼と並ばせるとアルゴスでなくとも灯台と蝋燭のように見えるかもしれない。
だけれど、だからなんなのだろう。僕がその意味を理解できないでいると、こちらを向いて、目を細めた。
「短足で体が重いから、蹴りより拳が効くんだよ」
彼はいたく真面目そうに言ったけど、僕はなんだかそれがとてもおかしかった。そしてその口ぶりからは、アルゴスの拳や蹴りを何時も貰い受けていることが想像できた。もしかしたら彼は、アルゴスの一派とはウマが合わないのかもしれない。
「キミは…?どうして、僕に親切にしてくれるの?」
尋ねてみると、彼は少し驚いたような顔で首を傾げた。
「親切。俺が親切かあ。リンチに荷担しないで傍観してただけで、ね」
皮肉めいた表情で、やや僕を挑発するように見下した。
なるほど。やっぱり彼も、少しは捻くれているのだ。
それでも、アルゴス達と比べるといくらもまともな品性の持ち主であることは明瞭だったし、今思うと僕は単純に、この短い時の中で急速に彼に惹かれていたと思う。
話し方のユーモラスさや落ち着いたふるまいなんかには興味がわいたと思うけれど、何よりも、彼の瞳にはこの短時間で何度も目を奪われた。
大人びた表情の中に時折見せる、何か、物憂げで物欲しそうな瞳。
街にいる野良猫みたいで、どうしても魅力的だった。
僕が何も言わないものだから決まりが悪くなったのか、彼は少し考えるような顔をして、喉元をポリポリと掻いた。
「…すまん。実は俺もここに来てそんなに経ってないんだ。あいつらともどうも、仲良くなれないみたいでね」
「じゃあ!もしかして、君もリンチされたの?」
興味津々な気持ちを抑えられずに聞くと、彼は一瞬だけキョトンとした。それは彼が初めて見せる年相応の表情だった。
やがて見定めるように、まっすぐに僕を見つめる。
鋭くて薄い、紫色の目。
竜胆の花のような薄淋しい色をしたその眼差しを向けられ、僕はたじろいでしまいそうになった。
「そうかもな。リンチ仲間だ」
彼は目の下にシワを浮かべて、はは、と笑った。
ここに来てずっと心のそばに感じていた緊張が初めて解けていた。体のこわばりや、張り詰めてさびついた顔も、彼の笑顔につられてほころぶのがわかった。
絶望の暗い色でいっぱいだった僕の体に、少しだけ明るさが滲んでいた。
遠い国に古くから言い伝えられる、多才で悪賢な神の名前を持つ少年。
ヘルメスと言葉を交わしたのは、これが初めてのことだった。