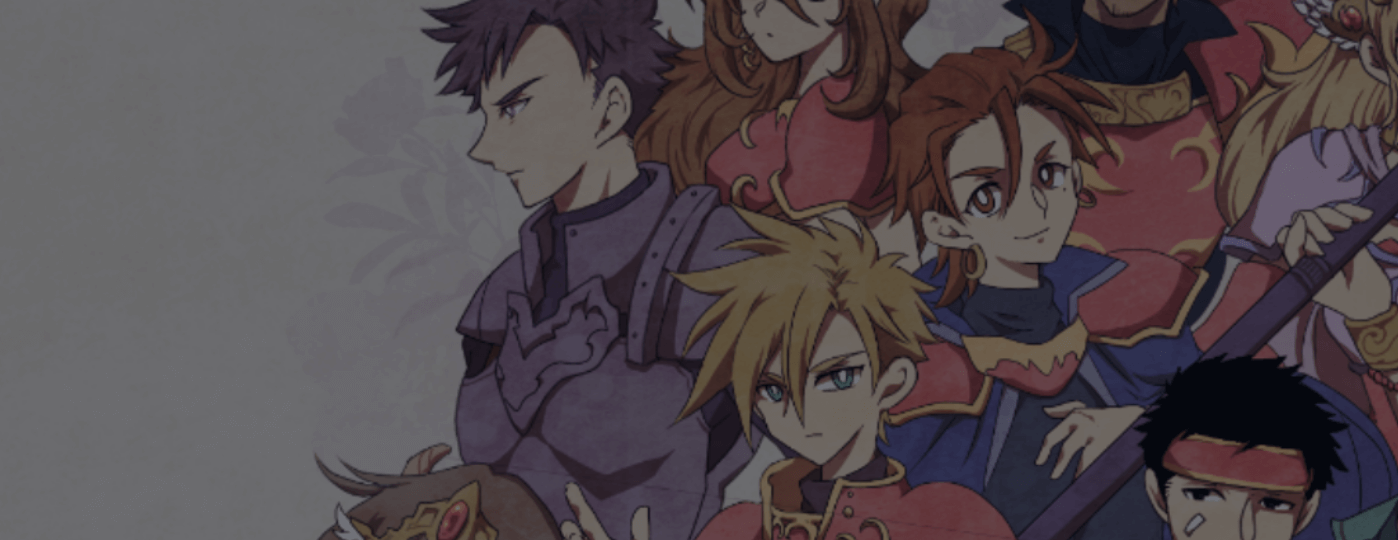2.ガル・ド・イド大陸
─────────ガル・ド・イド大陸全土が戦乱に荒れること数百年、国が生まれては死んでいき、罪無き人々の血が流れ、戦地には騎士達の遺体が積み重なる。そんな日々が永遠のように長い間、繰り返されてきた。
群雄割拠の時代と言えば響きは勇ましかったけれど、きっと誰もがこの大陸を平和に導いてくれる英雄を求めていたと思う。
物心ついた頃から、秩序や平和を諦めた大人たちの顔を見て育った僕は、特にそんなヒーローが現れてくれるのを夢を見ていた気がする。そういった英雄譚を綴った物語を読みあさるのも、大好きだった。
きっといつか、心のそばに何時も恐怖や不安を抱えていなくてはいけない日々から救ってくれる。そんな導きの火を灯してくれる。誰かが。
案外、その兆しは僕の人生の中では早くに訪れた。
大国アルマムーンの王・ダークフリードが即位して以来、アルマムーンはその勢力を広げ、戦乱の時代に終止符を打とうとしている。ダークフリード王はこの大陸全土の統治を豪語していて、戦争のない一つの国を作ろうとしていた。
そんな希望に満ちた話には尾ひれがつくものなのか、最近では夢物語のような噂まで耳にする。
ダークフリード王はこの大陸のどこかに潜むという異形のモンスターと契約を交わして、不思議な魔法にも似た力を召喚し、その圧倒的な武力を従えて各地を沈静化させているのだそうだ。
信じられない話だけれど、もしそれが本当なら、あるいはそれに匹敵するような力のある国なら、そしてその国が平和を掲げて剣を振るっているのなら、と。僕だけではなく、大陸の各地でアルマムーンに夢を抱く者は多かったと思う。
ところで僕の住む国はというと、そんなアルマムーンからは遠く離れた、大陸の南に位置する半島にある、小さな国だった。名を、ソロン国といった。
未開の地も多くて開発途上にあるけれど、昔から和平を結んでいた隣国ペンタグラムの庇護を受けている。といっても、それはもちろん、ていのいい言い方だ。
ソロンはいわば植民国だった。
軍備が統制されていないソロンは、他国からの脅威をペンタグラムに解決してもらう代わりに、物資の半分以上を搾取され続けている。
おかげで、王都以外の街や村には多くの貧民が溢れていた。
戸籍がないなんてことは、ザラだった。医療が発展してるわけでもないから大人になれずに死んでいく子供だって多かった。奴隷制度が古くから根付いていたから、富裕層による人身売買が廃れないし、所有物として扱われる子供も大勢いた。
ソロンはそんな後進国だったけれど、王都だけはかろうじてきらびやかさを保っていた。中心街にはそれなりの王城がそびえ、その周りには聖堂に修道院、職人や商人が集う商店が広がっている。
この国の修道院は教育機関も兼ねていて、そこで教育を受けられるのは、一部例外を除いて、十三歳まで、かつ、高い授業料の問題を解決出来る家庭の子供だけだった。
もちろん教室に通うのはみな、商人や貴族とか格式高い家柄の子ばかり。だけれどそこには、ただ、僕という一つの例外があった。
僕の父はそこで教壇に立つ教師だったのだ。その由縁があって、僕自身も勉学に勤しむ日々を送ることができていた。
毎日洗いたてでノリの張ったシャツを身に纏ってやってくる子供達の中では、僕はひどく存在感を放っていたようで、友人と呼べる存在は一人もいなかった。
しかも特例ということで、僕が教育を受けるには、条件があった。一言で表すのならば、雑用係に任命されたのだ。
僕たち親子には、修道院の隅に物置小屋のような一室が与えられていて、僕は今までのほとんどをそこで、めまぐるしく過ごしていた。
朝は、鶏が鳴くより早くにベッドを出て、修道院の家畜小屋へ向かう。そこで鶏の卵を回収し、ヤギのミルクを絞り、家畜を世話する。それが終わると、次は菜園で収穫できそうな豆や薬草を見繕って、卵と一緒に調理場のシスターに届ける。
朝食の準備を手伝い、出来上がった質素な料理が食卓に並ぶ頃には父も席についており、そこでなんだかよく分からない神への謝辞を口にしてから、ようやく、朝ごはんにありつくことができる。
授業は正午からだったので、それまでは修道院中の衣類やシーツだとかを洗濯したり、トイレの掃除をしたり、やれる雑用をこなしていく。
疲れ果てる頃にようやく授業が始まって、夕方になるとまた食事の準備や後片付けにせっせと走り回り、僕が本当の意味で自由だったのは空がとっぷりと夜に落ちて、星がきらめく頃だった。
それでも、辛い毎日だなんてことは、決してなかった。
明日食べるものへの不安で眠れない程貧しい人がいることを考えると、穏やかな毎日ではないものの、僕は、幸運と言って良かった。
字の読み書きが出来ない大人だっている時代、詩を朗読したり、国や大陸の歴史を学んだり、計算のドリルを解いたり、そんな時間が確約されているだけで、僕は、贅沢だった。
夜のわずかな自由の時間には、父と物語を読んだり、父が得た大陸各地の情勢を聞いたりした。声を潜めて、眠りにつくまでのその時間を、二人で課外授業だなんて言っていた。
けれど、その日常は突然壊れてしまう。
教育制度が、つい最近、廃止されてしまった。
というのも、ソロンでも皆兵制度がとられるようになったのだ。健康な成人男性は三週間の訓練を受けた後、北のペンタグラム国に従軍することが、ほぼペンタグラムの一存で決まった。
突如そんな体制を組んだのにも理由があって、とある国、がペンタグラムを攻め入るという物騒な噂が流れてきたからだ。
ペンタグラムは大陸でも随一の軍備を誇るとも言われていたけれど、それに攻め入ろうとしている、とある国、というのが厄介な国だった。
かつて軍事力で最強と名高かったレムリア国だ。
精鋭ぞろいのレムリア国騎士団を率いるのはガイア騎士団長という老将で、勇猛果敢にして知略に富んだ先導者だ。けれど、寄る年波にこそは勝てず、数年前にこの世を去ったことは大きな話題となった。
英雄の死後、ここぞつけ入る隙と見た各国は次々にレムリアに強襲をかけるも、そこで思いも寄らない返り討ちにあってしまう。
各国の猛将を一閃の内にして撃退したレムリア騎士団の新たな先導者は、まだ年端もいかない、僕のような少年だったのだ。
その少年というのはガイア騎士団長の実子らしく、晩年の忘れ形見として寄せられた期待をはるかに超えた才能を備えていた。
特に、闘いの中見せるそれは、神童が悪童に身を堕とす瞬間とも言われている。
名前は忘れてしまったけれど、彼もまた、ヘルメスと同じように神の名を授かっていた。
太陽の子、という彼の二つ名は、ここソロンまで及ぶほどだった。
その太陽の子率いる驚異が勢いづいて、ペンタグラムを取り込もうとしている。その噂が知れ渡ると、ほどなくして、ペンタグラム国王は万全を期すつもりで闘士のかけらもないソロンのほんのわずかな戦力をもぎ取って行ったのだ。
僕の父も。
類なく、迎軍に加わることとなった。
それがどういうことなのか僕にはよくわかっていたから、毎日何通も、届くかもわからないけれど、内容のない文字でいっぱいの手紙を書いた。
教師の息子ではなくなった僕は、修道院での居場所をなくし、父の友人である教父様の元へ預けられることになった。
そうしてやってきたのが、王都から三時間ほど歩いた辺りに広がる農村のはずれにある、小さな教会だ。
孤児や疎開児を預かる施設でもあると聞いている。
正午に街を出て、見慣れない地図と村人達を頼りにして、ヘトヘトになりながらようやくたどり着いたものの、僕はそこで驚くべき事実をシスターから聞かされる。
父の友人である教父様は、つい先日亡くなったのだ、と。
今は、さして信仰の深いようにも見受けられない若いシスターが切り盛りしているという。父の知人の元に預けられる気でいたのだから、追い出されるのでは、と思ったものの、シスターは笑顔で僕を迎え入れた。
また家族が増えるのね!なんて手を合わせて喜んでいたけど、この女の人は正気だろうか。
修道院でも感じていたけれど、聖職者は善人を気取ることで快楽を得るタイプの人間が多いと思う。
まだ事実を受け入れられないでいる僕をひっつれ、子供達を呼び集めて手厚い歓迎会を開いてくれたのが、つい先程のことだ。
その後、人生初のリンチを経験して、ヘルメスと出会った。
僕の教会での日々は、こうして始まった。