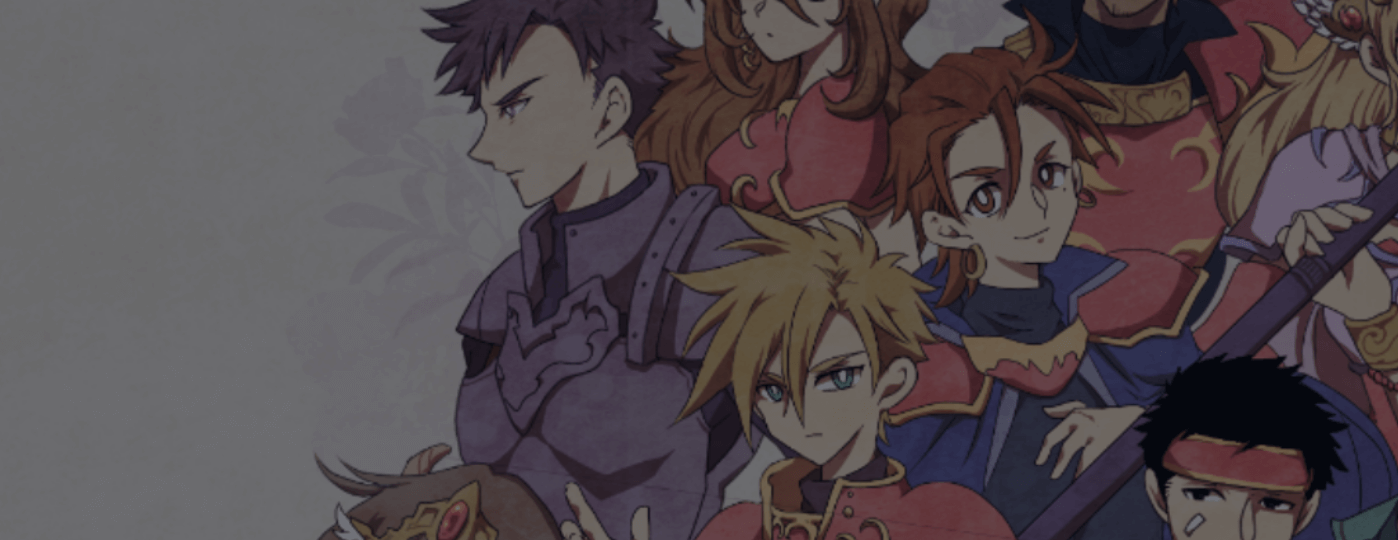6.レムリアの長い夜
城の中庭を突き抜ける外廊下を、カシスはひたに歩いていた。
陽はとうに地の向こうへ沈み落ち、中庭は宵闇に満ちている。
時折、一定位置に配備された衛兵の気配がするほか、人気はない。風に揺らぐ、草木の音さえもない。
あたり一帯ひっそりと水をうつ中、自身の足音と、甲冑の重なり擦れ合う音だけが鼓膜を刺激する。その音は、カシスの歩みに沿って規則的に反響し、かすかな余韻は中庭の茂みや、木立へと溶け込んでいく。
中庭に咲くジャスミンの香をはらんだ外気が、ひやりとカシスの肌を撫でる。花壇にはジャスミンのほか、バラやフリージアが春の彩りを見せていたが、それでもまだ夜の冷気は体に染みた。
この先に待ち受けているものを思うと、泡立つ肌は寒さのせいだけではないだろう。と、カシスは憂いた。
彼が歩みを進めるその外廊下は、レムリア国王宮、軍議の間へと続いていた。
レムリア国。
ガル・ド・イド大陸を大きく分断するレテ川下流から北東、険しい山々に囲まれた渓谷に位置し、一年を通して深い霧が立ち込める。その様子から「陽の昇らない国」と呼ばれていた。
霞の奥に息を潜める国の中枢は、堅固な造りをした城塞によって鉄壁を約束されている。谷底の都を囲うその城塞は、東西南北4つの砦を点に繋がっており、国民の住居区を、そしてこの王宮を隙間なく堅牢に守護していた。
4つの砦ではそれぞれ、レムリア国の中でも選り抜きの騎士4名が城主を務めている。
国の中軸たる彼らのことを、レムリアの霞切り裂く黎明が如しと人は言い、レムリア騎士団・黎明の四傑と呼んだ。
現下、王宮・軍議の間へと続く外廊下をひた歩くカシス・カーラントも、その一人である。
騎士団長の緊急招集に応じて軍議の間へ歩みを進めていた彼は、東の砦の城主であった。
時は数刻前、群青の天に、1つ2つの星が散りばめられる頃であった。
「カシス将軍に伝令、騎士団長閣下より招集です」
自らが城主を務める東の砦にて、カシスは遅めの夕食をとり終えたばかりであった。今後の進軍のルートを確認していると、王宮からの憲兵が忙しなく、切羽詰まった声で招集の令を告げた。
「今からか?あとは夜も更けるのみだというのに、一体何を集まることがあるのだ」
カシスは砦の自室で部屋着姿のまま、憲兵に投げやりに応じた。憲兵の方も適当にあしらわれたことを察し、ほとほと参った様子で、頬を冷や汗で濡らしている。
「一兵卒の私に軍議の内容までは分かりかねまして。閣下は四将軍みなさまにお声をかけられているようです。どうか本殿・軍議室へ参られますよう」
四将軍、と聞いて、カシスはぴくりと眉根を上げた。
とっさに、3つの見慣れた顔が、いやでもちらついた。
南の砦のグリッシーニ。
西の砦のキャロット。
そして、北の砦のチキータ。
自分と同じく、黎明の四傑と呼ばれた精鋭が皆、騎士団長の招集を受けている。憲兵はそう言った。
招集を受けた面子と告げられた時刻を思えば、その意図はよほどのことであろう。そもそも召集をかけた騎士団長本人がカシスより上の立場である故に、応じないという選択肢は元よりない。ここで憲兵と時間を潰していても無駄でしかなかった。
カシスは気分がどんより重たくなるのを感じながら、憲兵に労いの声をかけ、甲冑を身に、自らの砦をあとにしたのである。
王宮・軍議の間へと続く外廊下で歩を進めながら、カシスは熟れた果実のような赤黒い瞳に、憂いの色を浮かべていた。
招集の意図が気にかかるのもそうであったが、彼はそれよりも以前に、別の懸念を抱えている。今後の進軍のことであった。
レムリア軍は近く、南のソロン国・ペンタグラム国への侵攻を計画している。
カシスは騎士でありながらも、戦争行為そのものには後ろ向きであった。軍人向きではない自分自身を戦いの道に置くのは、時代を考えれば珍しいことではない。
誰もがそうであるように、カシスも自分なりの正道を歩むため、それを果たしたくて血を流している。平和のための犠牲と割り切るしかなかった。
ただ、気づけば一城の主にまでなり遂げてしまい、後に引けない状況まで来てしまっている。そこまで来ても、他国への侵犯を思うときはいつも気が滅入っていた。
剣を手に決意してから長らく時を経ても、それは変わらなかった。
そんな、もとより侵略行為に乗り気ではなかったカシスに、今宵の騎士団長の招集意図によっては更に気遣わしいことが増えるのだ。憂鬱な顔もしたくなる。
行く先に、白く小さな光が見えた。
薄暗く長い外廊下の終端に、軍議の間の灯りが溢れている。
軍議の間へと続く小さな門をくぐると、軍卓を囲う、招集に応じた3人の姿があった。黎明の四傑の者達である。
「我らが王子様、まだいらっしゃらないようだな」
カシスは辺りを見まわし、その3人以外に人気がないことを確認してから、口にした。
招集をかけた本人、まだ年若い騎士団長のことを、カシスは皮肉ってそう呼ぶことがあった。本人の耳に入れば間違いなく首が飛ぶような憎まれ口であったが、小さな反乱のつもりで、影ではよくそう呼んでいた。
「姫さんが倒れたそうだ。顔を出してからおいでになるんだとよ。使いがきたぞ」
顔に無数の傷を負った大柄な男が、カシスに一瞥をくれて言った。軍卓の上に足を放り投げ、腕を組み、気だるそうにあくびをかいている。
カシスの方へ向けた男の目には、光がない。生気がないとかそういうことではなく、特徴のある瞳をしている。奈落の底のような、濁ったどす黒い瞳で、野生動物のように表情がない。
敵意がないとはいえ、この瞳に真っ直ぐに見つめられると、身内のカシスでもわずかに背の寒くなることがあった。
この、人相も態度も悪い男は、南の砦の城主で、グリッシーニという。
顔に切り傷や火傷の痕を多く持つ彼は、全身もまたその通りである。
機会もないのでカシス自身その実態をまじまじと見たことはなかったが、時折露わになる腕には、確かに引きつった赤みや、縫い止めたような痕がいくつもあった。
戦いの最中、自慢の大剣をかついで嬉々と敵軍の塊に身を放り投げるグリッシーニを思い起こせば、不思議なことではなかった。
カシスはこのグリッシーニという男を得意とはしていなかったが、苦手であるというわけでもない。
狂戦士、レムリアのバーサーカー、人の皮をかぶった野獣、などと多数の悪名で呼ばれる彼だが、こうして何気ない会話に気軽に応じてくれるあたり、盟を同じくする四傑の中では比較的に付き合いやすい人間であった。
「なるほど、そうでなければ遅刻だったか。お姫様に感謝だな」
カシスは大きく息をついて、席に着く。
彼らが姫と呼ぶのは、未来の王妃を約束された乙女のことではない。年若い騎士団長を王子と、そしてその双子の姉君を姫と呼んで、遊んでいるにすぎない。
「カシスさん、遅刻は遅刻でしょ。団長の予定がずれてなかったら、どうなってたか」
陽だまりのような声が、カシスの頭上に降り注ぐ。
朗らかな掛け声とともにカシスの面前に歩みを止めた男の名は、キャロット。彼は西の砦の城主である。
絹のような柔らかな髪を耳下まで伸ばしているその容貌は若く、話し方もおっとりしているため、一見ではとても腕が立つようには見えない。
キャロットははかりごとを以って戦うことを得意とし、一部からは知将と呼ばれることもある。かといって、剣術を不得手としているわけでもない。
なにせ彼のイデオロギーは、謀略で事足りなければ武力で制する、という、柔和な顔に似合わない物騒なものだ。
盤上で投了したように見せて、盤ごとひっくり返すような、人を囃し立てるような戦い方をする。キャロットを策士と決め込んでいた敵は、突然さらけ出された猛威を理解できないまま、この世を去ることになる。
ただ、仲間内である分には世間的と呼べる性格であったし、特にカシスにとっては趣味のテーブルゲームの対戦に付き合ってくれる唯一の存在でもある。
チェスではキャロットにチェックメイトを突きつけられる日々であったが、どちらも懲りずに時間を見つけては盤を挟んでいた。
「遅刻といったってお前、このような時刻に招集されるとは思わんだろう。たとえ王子がおいでであっても、不可抗力さ。で、今宵のネタはなんだと思う」
「グリッシーニさんの部下が掴んだ情報が、それっぽいかなって。ね」
キャロットはカシスの隣の席へ座り、離れた位置のグリッシーニに微笑みながら、首をかしげて見せた。
グリッシーニは面倒そうに腕を組み替え、ため息をつく。
「バーミセリが言うには、我らが団長どの、船を一曹手に入れたそうだが」
「船?」
思いがけないキーワードに、カシスは素頓狂な声をあげた。
ところでグリッシーニが口にしたバーミセリという彼の部下は、諜報隊として城塞の外、山地に拠点を与えられている。山中を駆け巡るのが趣味でも任務でもあり、ふもとに降りることも多いため、城塞の外の情報には彼が一番詳しい。
「なんでも、海賊と交渉したようだ。おう、最近城に妙な赤毛の女が住み着いてるのを見るだろう。あれは、海賊のかしららしいぞ」
「ほら、この前一緒に見かけた、あの眼帯をした女のひとですよ、カシスさん。団長、賓客だとか言ってましたけど、まさか海賊の船長さんだったなんてね」
グリッシーニとキャロットが言うその女に、カシスも確かに見覚えがあった。
件の女と、カシスは先日、王宮ですれ違っていた。
女のほむら色の長い髪から、バラのように甘く、それでいて清潔な香りがカシスの鼻先をふわりとかすめた。
いい香りのする女であったことから、カシスはつい、甘い期待を込めて顔を覗きこんだ。そしてその甘い期待は、一瞬で敬遠の念へと変わった。
女は、整った顔立ちをしているのに、凶暴で、威圧的で、貫禄があった。左目を眼帯で覆っているのに、もう片方の瞳から覗く眼光は鋭く、血を求める者のそれであった。
カシスの横を通り過ぎていく後ろ姿にも隙がなかった。腕が立つのだろうと、すぐにわかった。
「彼女、海賊だったのか。ああ、思えば野蛮そうな女だったな。それにしても、王子様は海賊なんかと手を組んでまで、船をどうする気だろう」
「どうするって、まさかボトルに入れるわけでもあるまい。海を行く必要が出来たんだろうが」
顔に似合わない冗談を言うグリッシーニに、キャロットが声を立てずに笑った。グリッシーニの面構えに愛想はないが、こういった冗談をよく口にするあたり、無愛想な性格ではない。
「海路をね。それで、どこに?」
「そこまで知るか。遅れてきたかと思えばとんと質問攻めしてきやがって。目新しい情報といえば、そいつだけだっての。おいキャロット、先刻お前に全部話してやったろう。おれに同じことを二度喋らせるな」
「そう言ってちゃんとお話してくれるグリッシーニさん、僕は好きだな」
グリッシーニは身震いをし、野良犬を追い払うような仕草で、手をふった。
近況を知っただけでも、面倒なことが起こりそうな気配がする。
グリッシーニの話を聞いて、肩を落としたカシスであったが、ふと、一人だけ大きく距離をとって佇んでいる女に、目を向けた。
その女はカシスが来ても、その方向へ顔を向けるどころか、視線すら微動だにしなかった。
今もなお、話に加わることもなく、1人時間が過ぎるのを待っている。
北の砦の城主、チキータ・ミクロス。
華奢な体つきと蒼白な肌が虚弱そうではあるが、彼女もまた黎明の四傑の1人たる実力者だ。
また、カシスとは郷里を同じとする、幼馴染の間柄でもあった。チキータのミクロス家とカシスのカーラント家は昔から深い親交があり、血族同然の付き合いをしてきた。
しかし、今やチキータにとってその事実は、まるで関心のないことであるらしい。
チキータは幼い頃、愛嬌のある可憐で心優しい少女であった。よくスグリの花と実のついた草冠を作っては、カシスを喜ばせていた。そんな日々を続けていると、幼心ながら、彼女を娶るのは自分だろうと自然と思うようになっていた。
だが穏やかな日々は、ある時を境に、突然終わりを迎える。
今のような、そっけなく冷淡な、人に関心のない性格になってしまった理由に、カシスは十分なほど心当たりがあった。
おおかた、戦乱の世が、理由ではあった。
「チキータは、何か知っているか?」
カシスは挨拶代りのつもりでチキータに声をかけるが、名を口にした瞬間ですら、なんの反応もない。妙に長く感じる間をおいて、ようやく「さあな」と、か細い声が返ってくる。
キャロットとグリッシーニが、懲りないな、と呟くのが聞こえた。
今のチキータは人付き合いを必要最小限に留める性格であるが、だからといって、寡黙や孤独を決めこんでいるわけではない。
戦地では指揮も機敏であるし、冷静で合理的な判断を下す彼女のことを、慕う部下も少なからずいた。
また、他の理由でも人望を得ている。
彼女が座する北の砦は診療所も兼ねており、チキータは普段そこで医者としての役割を果たしている。解剖学の権威でもあり、外科処置や薬物療法に長けている彼女を頼って訪れる国民は多い。
徹底して不要なコミュニケーションを避けてはいるが、言いようによってはまっとうな人物である。
たった一つの、難儀な性癖を除いて。
チキータには死体収集・臓器保存の癖があった。
遺体を腐敗の進む前に解体し、写生し、記録する。あるいは臓器の一部に防腐処理を施し、特殊な樹脂により標本化する。もちろん医療発展に貢献する行為ではあったが、行動原理は個人的な収集欲に起因していた。
解剖医でもある彼女が、そうであっても仕方ないといえばそうなのだが、その執着が、職業病の一言で表すには型破りなものだった。
チキータの拠点、北の砦の地下には、遺体の安置所がある。
そこで安置されている遺体は、彼女の患者だった場合もあるが、彼女の個人的な収穫である方が多かった。
昔気の迷いか、チキータがカシスに吐露したことがあった。
チキータはたまに、一人の人間に執着し、固執してしまうことがある。
一目惚ればかりするのだ、と本人は笑うが、淡い恋話などではない。
一目見て、どうしてもその臓器を暴いてみたいという欲望が抑えられなくなる者がたまにいるのだ、と笑うのだから。
それは筋肉質な若い男であることも、妖艶な美女であることもある。無垢な体の少年少女であることもあった。
そこに医学的な視線はなく、彼女の感覚を鳴り響くようにひらめかせた人間が、不幸にもその手に堕ち、やがて標本となって彼女の心を永遠に捕らえるのだそうだ。
この話はひそやかな噂となっており、チキータを死の外科医、と呼ぶ者も多くいる。
「うん、そろそろお見えになる頃かな」
チキータにまともに相手をされなかった行き場のないカシスが、一人でぼやいた。異端な幼馴染ではあったが、清純なころの幼い日々を共に過ごした記憶がそうさせるのか、カシスはチキータを放っておけない。
チキータにしてみれば余計なお世話なのかもしれないが、暖簾に腕押すような関係をもう何年も続けていた。いつか、また、スグリの草冠を作ってくれることを、密かに夢見ていた。
カシスのぼやきが空中に溶ける頃、まさに都合よく、廊下から重い金属音が鳴り響いた。
その場にいた者は一同、席を立つ。鳴り響く足音に、耳を澄ます。
かしゃん、かしゃんと仰々しい響きを放つのは、騎士団長の足音で間違いないだろう。
カシスは、大げさに鳴り響く足音の後ろに、ひっそりと付き添う足音を聞いた。使用人が扉をノックしたときのような、とん、とんと小気味好いリズムがかすかに鼓膜を揺るがす。
「どうやら、客人もいらっしゃるようだな」
カシスがそう口にしたのち、二人の男女が軍議の間へと足を踏み入れた。
騎士団長アポロンと、件の女海賊であった。
「待たせたな」
アポロンは、若く、瑞々しい生気に満ちた声を発した。
長たるに相応しい恰幅、身のこしらえ、重厚な風情。
大英雄と名高かった前騎士団長ガイアの実子アポロンには、その一つ足りとも持ち合わせがない。
わずか齢十五の彼が携えているものは、青臭さと威厳の入り混じる奇妙な覇気と、絶対的な武力のみで、だが、それだけでレムリア軍の頂点を勝ち得ていた。
一同はみな、自分よりはるかに年の離れたアポロンに対し、頭を下げた。
こうべを垂れながら、カシスはわずかに、屈辱を自覚する。
こうしてアポロンに頭を下げると、いつも断片的に脳裏に浮かぶ。
見た目少年でしかない彼に、しかし剣技ではただの一度も敵わなかった事実。そしてそれは、一度や二度ではない。
黎明の四傑は皆、戦術においてそれぞれ取り柄があった。
力はグリッシーニ、智謀はキャロット、技はチキータ、速さはカシスに、それぞれ最も部があった。
だがその彼らの長所を以ってしても、今までアポロンの剣に打ち勝ったことはない。アポロンが備えていたものが、万能の才であったからだ。
天より与えられた才。
言葉にするといたく陳腐であった。ただ、アポロンと剣を交えたことがある者は、その言葉を笑うに笑えない。
まだ未熟な子供の体に、大英雄ガイアの素質の全てが凝縮されていた。
憑き者ではないかと恐れる声、神童と称える声。それらによって、アポロンの強さは、レムリア国の外まで知れ渡っていた。
「姉上が体調を崩されてしまってな。見舞っていたら、そなたらを呼び寄せたこと、ふと忘れてしまったわ」
アポロンは中央に置かれた玉座に重々しく座り込み、放り投げるようにして脚を組むと、声だけでからからと笑った。
アポロンには、時を同じくして生を受けたアルテミスという双子の姉がいる。
神童と崇められるアポロンとは違い、アルテミスは、凡弱でか弱い少女に過ぎない。王城の離宮に住まうことを許され、ほとんど顔を出すことはない。
アポロンの欠点を挙げるのであれば、年若さを除けばこの姉アルテミスを溺愛していたことぐらいである。
一般的な姉弟愛とはかけ離れた様子であったから、その異様さが人の目をひいていた。
今回のようにアルテミスにかまけ、他をおざなりにすることは珍しいことではなかった。
「面をあげろよ。今宵の話は長くなる、楽にしろ」
アポロンのその一言を待っていたかのように、グリッシーニは椅子の上に腰を下ろし、おもむろにあぐらをかいた。続いてキャロットが席に着き、頬杖をつく。
アポロンは慇懃な弱卒よりも非礼な勇将を好んでいたから、部下の横柄な態度には気にも留めず、話を続ける。
「まずは、そうだな。顔合わせといこう、アテナ」
アポロンが声を張ると、アテナと呼ばれた赤毛の女海賊は玉座の側に控え、四傑の面々に禍々しく余裕のある顔を向けた。
カシスは真正面からじっくり彼女を見据え、改めてその気迫を強く感じ取った。
グリッシーニがキャロットの方を向き、本人には聞こえないくらいの声で、お前と五分、とにやけた。
「我が名はアテナ。北海を統べる覇者、アイギス海賊団の長である。今宵、貴国レムリアの心臓とも言えるアポロン殿、そして黎明の四傑と名高いあなた方に、協定を組んで頂きたい覚悟をして参った」
アテナと名乗った女海賊は、その立場にそぐわない邪心ない声で宣言した。アテナのそばで反り返るアポロンが、くっくと笑う。
グリッシーニの部下、バーミセリからの情報を事前に聞いていなければ、カシスは今頃、仰天のあまり閉口していたことだろう。思い浮かぶいくつもの不平を飲み込み、アポロンに向きなおる。
「アポロン様。海賊と結託することで王のお怒りや民の不満を買うのは、この際言及しないことにいたしましょう。ただ、そういった反感に勝る利点が、彼女と手を組むことで、得られるということでお間違いないですか?」
「カシスさん、それ充分言及してる」
カシスは自身を非礼ない実直な男であると自覚していたが、アポロンに対する口ぶりは、敬服よりも、年若い弟を持つ兄のそれであった。思わずキャロットが口をはさむ。
だがそうまで言われても、アポロンは眉根を寄せることもなく、依然と痛快そうな顔である。
「確かに、おれも徒党を組むような真似は好かん。加えて、事もあろうに賊ごときがこの俺と手を組みたいなど、厚顔さにあきれかえっていたものさ。はじめはな」
薄い唇を歪ませて、アポロンはアテナに挑発するような顔を見せた。
「団長?要点を」
消え入りそうに小さいのに、何故だかよく通る声で口を挟んだのは、チキータであった。ここへきてようやくまともに口を開いたかと思えば、無駄なやり取りを好まない彼女の催促の一刀両断である。
「長くなると言ったろうチキータ。しかし、そうだな。アテナ、話してやれよ。我が騎士団の連中を説き伏せてみろ。このおれを口説き落とした時のようにな」
アテナは若干苦い顔をして、頷いた。
「話を急く者もいるようだ、かいつまんでお話ししよう。あなた方はこのガル・ド・イド大陸の西方、悪魔の棲む島というのはご存知だろうか。周辺の潮流は激しい渦潮で上陸が難しく、訪れる者も、還る者もいない。我々海賊には馴染みのある噂だ」
話を区切ったアテナは、四搩の方を見回した。
彼女とアポロン以外の誰も、思い当たる話ではなかったようで、肩をすくめたり首を傾げたりしている。
その様子を察し、アテナは再び口を開く。
「ではガル・ド・イド大陸のどこかに潜む魔物の話は、聞いたことがあるだろう。数年前から、大国アルマムーンの王がその魔物と契約し、戦力にしているという話だ」
大国アルマムーン、と、アテナが口にした時、アポロンの口元がわずかに痙攣する。
「その話って今じゃどこでも聞きますけど、ただの比喩なんじゃ?あの国、王様自身も雄剛な人らしいけど、ちょっと前に叙任されたゼウスっていう若いのが恐ろしく強いって。魔物云々の噂、ちょうどその頃から広まってるしね」
キャロットが顎に手をあて、考えるようにして口を開いた。それに応じて、グリッシーニがうんうんと頷く。
「魔物と例えられるほどの使い手なんて、ヤッてみたいもんだよな。アルマムーンの連中、とっとと軍勢率いて攻めてこねえかな」
野蛮な会話に、カシスは軽くめまいを覚えつつも、興味があった。ゼウスの名には、かねてから惹かれていた。その名のあとに必ずついてくる武勇伝を聞くたびに、どんな男だろうかと思想を巡らせた。騎士としての性なのか、戦争を嫌い、平和を願いながらも、腕の立つ者への戦意は自然と湧いた。
キャロットとグリッシーニが軽口に浮かれるところを哀れむように横目で眺め、アテナは続けた。
「我々も、そう、噂でしかないと決め込んでいた。大商会ゴールデンハートと対峙するまでは」
ゴールデンハート商会。アテナが口にしたこの商会は、大陸西方では有名で、アルマムーンを拠点に大陸外を旅する組織であった。アルマムーン国の援助もあり、軍艦に匹敵する商船を持ち、海賊でも迂闊に手を出すことはない。
また近年、独立していたアルマムーン水軍と合併し、本格的に武力を携えたことで、急成長を遂げた勢力である。
「やつらはもともと西海をうろついてたのだが、領域を北にまで伸ばしてきた。少々目障りになってきた故に…我らがアイギス海賊団、総力を挙げて叩いたのだ。戦局は終始我々が優勢、戦いの終わりは見えていた。しかし、しかし…」
アテナはそこで、言葉に詰まる。
記憶の中の忌まわしいものを思い起こしたように、唇を噛む。
アテナの戦慄とも悔恨ともとれる表情を見て、カシスは思いつきを口にした。
「まさか、魔物がいたとか」
その言葉に、片方だけ覗いた目を見開き、アテナは頷く。
ほんの一瞬、悪夢に怯える幼い少女のような顔をした。露わにしたしなやかな脚は、よく見ると、か細く震えていた。
キャロットとグリッシーニは嘲笑の表情を消す。呆れ顔で目を伏せていたチキータも、顔を上げる。
「魔物は…いた。私たちは見た。あの時、劣勢だったゴールデンハート商会のリーダーは、意を決したように…たまごほどの小さな玉を掲げた。そう思うと、途端にその場の空気が一変した。本当に、空気が淀んで、一瞬にして暗雲が垂れ込めた。何事かと思う間もなかった、閃光がひらめいて、海面を撃った…そしてそこに、そこには………異形があった。本当だ、本当にいたんだよ。あれは、悪魔だった」
アテナは思わず身震いをして、むき出しの肩を自身で撫でた。目を伏せ、たどたどしく話を続けた。
「結果的に、私たちは半壊した。本船が無事だったのは、幸運であった。無様であることを恥とも思わず、逃げ出したよ。そう、化け物は…大きい、蛇のような胴体に、人間の女の、上半身がついていた。尾の方には、無数の蛇頭のようなものがおぞましくひしめいていた。その尾で海面を叩いた水しぶきだけで、瞬く間に十人もの仲間が吹き飛んだ。矢を放てども放てども、その体を貫くことは出来なかった。やっとの思いで近づいてやつに刃を突きたてた者は、太い胴体に巻かれ、体まるごと、砕かれた」
堂々としていたアテナの威厳は、見る影もない。青い顔をして、遠い目で自身の記憶を見ていた。
現実味のない話ではあったが、淡々と話す彼女の様子の痛々しさには、重みがあった。カシスは児童向けの物語を想像するような気持ちではあったが、目の前の話ぶりを見ていると、信じてやりたい気持ちがあるのも事実だった。
ちらりとアポロンの方に目をやると、彼は微笑み、まあ聞けと言わんばかりの顔でカシスをたしなめた。
「私たちは死んでいった仲間のためにも、ゴールデンハート商会を許すことはない。ついてはアルマムーンがこの大陸を統治しようなどという目論見にも、全力で抗っていくつもりだ。だから、私たちの報復に、あなた達の力を借りたいのだ」
悲壮にくれるアテナに対し、ただの返り討ちじゃないか、という言葉を、カシスは飲み込んだ。女性に縁深くないカシスでも、感情的になっている女にかけるべきではない言葉はわきまえている。
できる限り逆撫でしないように、言葉を選びつつ、口を開く。
「その話が本当であるとしよう。我々といえど、人の身でそのような化け物相手に対抗できるものだろうか」
訝しさを隠せないカシスに、アポロンが口を挟んだ。
「カシス、どこぞの文明が残した法典に、こんな至言がある。目には目を、歯には歯を。敵が異形を操るのであろう?ならばこちらも、この世ならざるものの力を扱えばよい話。おれはその異形の力、なんとしてでもこの手におさめるつもりだ」
力強いアポロンの言葉に、カシスはさすがに辟易した。いくらアテナが真に迫る物言いをしたとはいえ、魔物の話を鵜呑みして更にはそれを従えようとは、笑止の沙汰ではないか。
「雲を掴むような話です。この話、突然どうしてまるきり信じられましょうか」
「信じる必要があるか?この女の言うことが皆目出鱈目であった暁には、こやつの首をはねるまで。神の嫉妬か、忌まわしきアルマムーンの輩が持つ力を、このおれが手にしていない。それが事実である方が、よほど肝要であると思わぬか」
もはや何を言おうとも、アポロンの声に、瞳に、揺るぎはない。頑としてアテナの言い分を聞き入れるつもりであった。こういうところが子供なのだ、とカシスは内心毒づいた。
その様子を見て、キャロットが宥めるようにカシスの肩を叩く。
「カシスさん、こういった類の話は疑いだしたら先へ進まないもんですよ」
「お前は…なぜそう、呑気なのだ。この途方もない話、一体どう噛み砕けばいい?」
「まあまあ。本当に途方もないのか、まずアテナさんの話をまとめてみましょうよ。第一に、魔物は、その身を常に現世に置いているわけではない。商会のリーダーが掲げたっていうキーアイテムを使用することで、魔物ははじめて姿を表すことができる。つまり、悪魔召喚のような形態をとっているわけですね。噂の通り、人と魔物で、何かしらの契約を結んでいる可能性が高い。第二に気になるのは、その召喚のタイミング。敵はピンチになるまで召喚を出ししぶっていた。このことは、その召喚には限度や制約がある、あるいはコストがそれなりであることが伺えます」
焦燥にかられるカシスをよそに、人差し指を口元に当てながら、キャロットが悠然と状況をまとめにかかる。
「僕らがその力にあずかるには、そのキーアイテムを手にいれるのが第一。そしてその使用条件を満たすのが第二。おおよそ第一の手がかりは、最初にアテナさんが言っていた、悪魔の棲む島ってとこでしょうか」
邪推のない表情のキャロットに見つめられて、アテナはややたじろいでから、答えた。
「ああ…ああ。そうなるな。情報屋を雇い、あらましを調べさせてわかったことだ。アルマムーン王に魔物の噂がついてまわるようになったのは、水軍を用いた遠征のあとだったという。その海路は西方、悪魔の棲む島でないかと予測する。海の北西は、すでにゴールデンハート商会の領域。あなた方は南のペンタグラム・ソロンを落とすのだろう。それが叶えば、南海域から迂回してその島へ向かうことが可能。上陸までのことは、我々に任せてもらうほかない。ただし、情報屋を雇っても、位置以外のことは未だ不明瞭。不安が残るのだが、だからこそあなた方レムリアの心臓部に力を貸していただきたいのだ。確かに途方もない話だが、これが実を結べば貴国も私たちも、人ならざる力を手にすることができる」
言い終えたアテナが深く頭を下げると、誰からともなく皆、顔を見合わせた。各々が様々な顔色を浮かべていたが、相変わらず疑心に満ちていたのはカシスのみであった。
「俺は異論ないぜ。魔物の力を借りたいとは思わんが、そうまで強いのなら一度手を合わせてみたいもんだ」
「僕も、今のところは賛成。きちんとした下調べと計画は、ペンタグラムを叩いてからでも遅くないでしょう。それに、団長がもう乗り気なんだったら、決定でしょ」
グリッシーニとキャロットは、依然と陽気であった。程度の重さを感じさせない彼らの調子は、アテナの顔をほころばせた。
アポロンがチキータの方を見ると、彼女はそっけなく目を伏せた。
「私は、どちらでも構わない。強いて言うなら、蛇のような半身を持つ魔物…骨髄とか血液に薬効があるかもしれない。従えたいというよりは解剖してみたいな。そういう意味では、非常にそそられる。賛同だ」
面倒ごとを嫌うチキータが同意したことは、カシスにとって予想外であった。頼みの綱は断たれてしまい、皆が自ずとカシスの方へ顔を向ける。ことさら、アテナの懇願するような表情が痛かった。
「煮え切らないのは、カシス。そなただけか」
「私は、アポロン様が決めたことに逆らうつもりはありません…ただ、ソロン・ペンタグラムへの侵攻が控えているというのに、二手も三手も先の話をしてもいかがなものかと」
「そなたは心配性よなあ。いつまでもこの霧の立ち込める谷底にこもっていて何になる。つまらん小競り合いの時代を終わらせるために、おれたちは毎日血を浴びているのではないか?安寧に要るのは、圧倒的な力。そのために今こそ奔走することが、正義ではないか」
アポロンの独自の理想譚に、カシスは興味がなかった。穏健を望むカシスにとって、どんな建前を並べても、血を浴びることへの忌避を覆すには至らない。
しかし、黎明の四搩とまで呼ばれる立場にいる以上、そもそも反論が許されないことは知っていたのだ。これ以上ごねても、結局何も変えられないことは、最初から決まっていたのだ。
「…仰せの通りです。もう何も、言うことはありません」
カシスは覚悟をきめ、アテナの話を受け入れた。勿論、納得したとは言えなかった。
カシスの賛同を聞いて、アポロンは満足そうにため息を漏らす。
「よかろう。アテナ、お前もペンタグラムへの進軍には付き添うてくれるな」
「無論、半数になってしまったとはいえ、アイギス海賊団総員で従わせていただくつもり」
「そうか、では明日にでも全軍を招集し、開戦の宣言としよう。お前のことは、その折りに紹介する」
アポロンとアテナの会話を聞きながら、カシスは余計に重くなった肩の荷に耐え切れず、気を落とした。どうなろうとも、決定権が無いのだからもはや自分の知ったことではない。投げやりに放心を決め込んで宙を仰いでいたが、しばらくして思いついたようにアポロンが言う。
「カシス、この件、王にはそなたから伝えておけ」
「はあ…は、わ?わ、私よりアポロン様の方が御目通りやすいでしょう。それに、私からお伝えしたところで、ご納得いただけるかどうか」
「好き勝手するようになってから、王はどうもおれを避けているようでな。僭主を恐れているのかもしれんな、はは。面倒だ、頼んだぞ。おれは姉上に顔を出してくるからな」
言い捨て、半ば逃げるようにして軍議の間を後にすると、アポロンは豪快な足音を立ててアルテミスのいる離宮へと飛んでいった。
アポロンが姿を消すと、チキータは小さく息をついて、無言のまま北の砦へと帰っていった。
「さすが、王へのご報告まで任せられるとは。王子様の一番のお気に入りなだけあるじゃねえか」
「ねえカシスさん、王様の様子どうだったか、明日聞かせてね」
キャロットとグリッシーニは、ひときわ哀れんだ瞳を向けた後、思い思いに嘲った言葉を捨て、退散した。
「…気苦労の多そうな軍だな」
しんと静まり返った軍議の間に響く、アテナの声が、やけに遠くに聞こえた。
夜分に国王への謁見を申し込んだカシスが憎まれ口を浴び終えたのは、日をとうに跨いで久しい時刻であった。