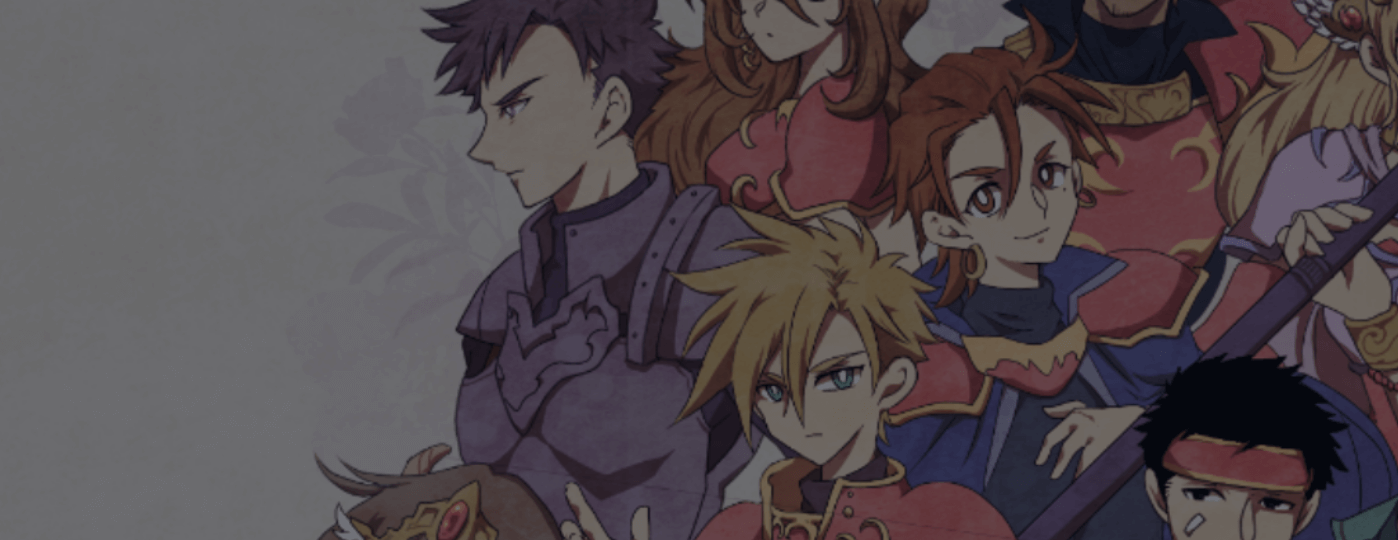4.コンドリュー・カンパニー
香ばしい藁の香りに包まれて、その夜、僕は夢も見ずに眠りこんだ。
藁を駆り立てた茎の先端がチクチクと肌を刺すものだから、ヘルメスが新調してくれた藁ベッドの寝心地は、とても快適とは呼べないものだった。それでも、その寝心地の悪さが僕の眠気を遮ることは、夜中の間中一度もなかった。
王都からこの教会への移住、荒くれた子供達からの歓迎、夜の森でのヘルメスとの協定。
昨日一日にして、慣れない多くのことがあった。
寝床に着いた時、藁ベッドに誘われるようにして僕は意識を失った。
鳥のさえずりとアルゴスのいびきを交差に聞きながら目を覚ました時には、白い朝の光が窓から差し込んでいた。
まだウットリとした頭のまま隣の藁ベッドに目を向けてみると、そこにルームメイトの寝姿は既になかった。手を伸ばしてみると、暖かさだけがそこにはあった。
僕は、身を包んでいたくたくたのタオルケットから抜け出した。アルゴスや他の子供達をちらりと覗くと、彼らはまだ夢の最中のようだ。
朝の冷気に体を震わせながら聖堂まで出てみると、ヘルメスの姿がそこにあった。外への扉に手をかけている。こんな早くから、どこへ出かけるのだろうか。
「おはよ…随分、早いんだね」
僕がひとつ伸びをしながら挨拶を口にすると、ヘルメスは眠気を飛ばすような仕草をした。
「どこかの誰かに、とんでもないお誘いを受けたからな。ただちに本日より、作戦を開始する」
ヘルメスは演技がかった口調で、僕に敬礼して見せた。
たたえていたヘルメスの軽い笑みを見て、僕は少し気恥ずかしい心地で昨晩のことを思い出していた。
この国を出て、ヘルメスと一緒にアルマムーンに行く。
一晩経つと、あれだけ猛っていた気持ちも、落ち着くものだ。
昨夜は、自分でも途方のないことを口走ってしまっていたな、と思う。
もちろん、大風呂敷を広げただけのつもりはないのだけれど、よくよく思い返してみると、自分に酔っていて、ナルシシズムを飛散させた口ぶりだった。
それでいて、計画もなければ、行った先でどうするのか、具体的な目標などなにひとつない。本当に思いつきで幼稚な憧憬を、よりによって同い年の、出会ったばかりの少年にあけすけ曝け出してしまったことで、僕には少しだけ面映い気持ちがつきまとっていた。
そんな僕の内心など全く気にすることもなく、ヘルメスは揚々と教会を出ていった。近くの川辺まで行くというので、僕もその後を追うことにした。
その川は、教会からでもせせらぎを耳にするほど近くにある。川幅は両腕を広げた程の大きさしかないにしろ、僕らの生活用水としてはとても便利な位置に流れていた。
朝の、形ない光に輝いた川の水面は、キラキラしている。見ているとだんだんと眠気も薄れていく。目をこらすと、小さな川魚が数匹、川の流れに揺らいでいた。
四月に入ったばかりの今、まだ朝は肌寒くヒヤリとするものの、清々しい空気の香りがなんと気持ちいい。岩場の側には、川の水しぶきを受けたスミレが瑞々しく花弁を開いている。緑の少ない王都では見られなかった春の兆しが、僕には少し珍しかった。
僕らは川の水で顔を洗って軽く体を拭き、お互いの寝癖をああだこうだ言いながら直しあった。
ヘルメスの髪は短く太く、僕は彼の襟足を少し濡らし、ものの数分で理髪師としての時間を済ませてしまった。
一方、僕の髪はいわゆる猫っ毛というやつで、一晩経つと芽吹いたツルのように躍動してしまうのだ。ヘルメスは逐一文句を口にしながら、僕の髪の毛と長いこと格闘していた。
「初手にしては、悪くない案があるんだ。今日早速、街に行こう」
僕の髪を慣れない手つきでセットしながら、ヘルメスは言った。
僕らの一大計画は、その穴だらけの壁面を埋めていく為にまず、先立つものを必要としている。
旅路を練るにしても、この大陸の地図もなければ、詳細な各地の情勢もわからない。考えなしに歩けば、たちまち抗争に巻き込まれてしまうだろう。
そもそも長距離を移動するための資源として、何をどれくらい要するのか、それにいくら必要なのかもわかっていない。
そんな暗雲の中、ヘルメスが提案してくれた内容というのは、金策と情報収集をいっぺんに解決する夢のような指針だった。
僕はその計画の一端を、目が眩むような思いで聞いていた。
なんにせよ、すぐさま、セント・ロギオスの街へ向かうことにした。
川辺から教会へ戻った頃には村の人々も目を覚ます時間になっていて、流石にアルゴス達も、のそのそと藁ベッドから抜け出していた。
僕らはシスターから黒パンをひとつずつ受け取って、教会を出た。その際アルゴスに「お兄ちゃんの代わりが出来たのか?」なんて声をかけられて心底嫌気がさしたけれど、隣のヘルメスの方が僕よりよっぽど首筋を寒くさせていたのがおかしくて、なんだか毒気を抜かれてしまった。
僕らがこれから向かうセント・ロギオスの街は、ソロン国の最北部。より、ペンタグラム国へ近づく位置にある。
ヘルメスによると、その街には、訪れた者の目を引く建物があるという。書物の製本や印刷物を扱う新聞社、コンドリュー・カンパニーだ。
コンドリュー・カンパニーは国が組織した業者とは違って、街の職人や記者、諜報員が集って出来たギルド構成の新聞社だった。その成り立ち故に情報には規制がなく、手書き新聞なんかは日銭の範囲で誰でも手に入れることができる。
そんな理由からか、国からは鬱陶しく見えるようだった。度々新聞社の運営には圧力がかかっている。今は、社員と市民の団結によってなんとか廃止を免れている状態だった。
コンドリュー・カンパニーは普段、多くの記者や職人が出たり入ったりで忙しない。けれど徴兵令が出てからは、人手が割かれて、随分ガランとしてしまっているようだ。
その一方では、レムリア国の進軍は刻一刻と迫ってきている。そんな確かかも分からない噂だけが広まって、今、ソロン国民は現状を把握出来ずに不確かな情報に憂うことしか出来ていない。
人手不足が原因で張り巡らせなければならない情報が伝達されず溜まっているとしたら、コンドリュー・カンパニーとしても使える人間が一人でも多く欲しいはずだった。
それが、例え僕のような子供でも。
「だからって、いきなり僕みたいのを雇ってくれるなんて、夢のような話なんじゃないかなあ」
道すがら、僕は黒パンをかじり千切ってヘルメスにぼやいた。太陽が昇り始めて、空気の色が濃くなっている。
先ほど川辺で聞かされた計画の第一段階というのは、僕がコンドリュー・カンパニーで働いて資本を積み立てる、という、僕の思っていた以上に大味で怖いもの知らずな内容だった。
「そうさ、何しろ夢みたいな話から始まったことだからな。夢ついでだよ。なに、どうせだから大きい魚から狙おうぜ。釣れたら儲けもんだ」
すでに黒パンをまるまる口の中に放り込んでいたヘルメスが、むぐむぐさせながらあっけらかんと言う。
「エサが僕じゃ、釣れる魚も釣れないんじゃ」
「腹が空いてりゃ、なんだって食うもんさ」
こんな干からびた黒パンでもな、と言ってヘルメスは皮肉を込めて笑った。
そんなうまい話があるわけないと思う反面、ヘルメスが言うと、万が一もある気がしてくる。彼の言葉は不敵で途方のないものでも、その口ぶりは、余裕と説得力がある。まして、他に名案があるわけでもない。今は思い当たることは何でもすべきだった。
それでも、胃の底で小さな不安が湧き上がるのを、僕は自覚していた。
釈然としない想いを拭いさりたくて、頭にかぶったキャスケット帽を太陽に向かってひるがえす。
このキャスケット帽は今朝、教会を出る寸前になって、ヘルメスが僕にかぶせたものだった。
「あの街に行くなら、その頭は隠した方がいいな」
そう言って、ヘルメスは自分でセットした僕の金色の髪を、帽子の中へしまい込んでしまった。
王都でも、父から決して近寄るなと言い聞かされていた区域はあった。いわゆる、無法地帯。アウトローの領域だ。
けれど、セント・ロギオスの治安の悪さというのは、その比ではないようだ。
この国ではまだ富裕層による人身売買が横行している。特に、セント・ロギオスでは人攫いを稼ぎ口にしている輩が少なくないらしい。小さい子供や女の人を攫って王都の貴族や国外に奴隷として売飛ばし、薄汚れた金を手にするなんて事が、平気で起きている。
そして、そういう輩が特に目の色を変えて値踏みしてくるのが、僕のようなブロンドヘアの子供だそうだ。
今朝それをヘルメスに聞かされた時、昨晩あんなに上を向いていた気持ちが、みるみると下向きになっていくのがわかった。
売り物としての自分の価値を、平気で受け止められる精神力を僕はまだ持ち合わせていない。
もちろんヘルメスに他意はなく、事実を教えてくれただけだし、もし心構えがないままセント・ロギオスへ行って突然その悪意を突き立てられていたと思うと、ぞわりとする。
それでも、自分が、まるで愛玩動物のような尊厳のない生き物だと言われたようなイメージが、僕には拭いされないでいた。
「夜道や人気の少ないところは避けろ。あの街では、なるだけ、そばを離れるなよ」
セント・ロギオスが僕にとっていかに魔の巣であるかを説いた上で、ヘルメスは、物心ついたばかりの幼子を扱うように言った。
大人ぶらないでくれ、なんて、口にする気すら起きなかった。
その話は、セント・ロギオスへの畏怖の念が僕の体に刻み込まれる理由としては、充分なものだった。
一時間ほど歩くと、セント・ロギオスの街に入る、大きな石橋が目についた。
大きさこそそれほどでもないにしろ、しっかりとした石造りだ。馬車二台は行き交う広さと、渡りきるのに数十秒はかかるだろう長さがある。川面からの高さは、だいたい二十メートルほどだろうか。
年季は入っていて、ツタが絡みついて石の表面も風化しているのがそれらしい。
その石橋を渡ってすぐに、大通りがセント・ロギオスの街を突き抜けていた。
人通りが少ない代わりに、店主が不在の露店と看板の撤去された店が多く目についた。路地裏には、意味ありげな目線をこちらに向けてくる中年の男や、薄着で化粧の濃い女の人がタバコをふかしている。
とっさに今朝のヘルメスの言葉が思い出されて、足がすくみそうになる。
「目、あわせるな」
僕が怖気付いていると、ヘルメスに小声で一喝された。いかにも不安そうに見せると、付け入れられるぞ、と。僕は出来るだけそれらの不安を煽る要素を目に入れないようにして、大通りをまっすぐに歩いた。
人のまばらな大通りを進むと、広場に出た。集う街の人々がいないからか、ガランとして寂しい印象だ。
コンドリュー・カンパニーは、その広場の一画にあった。
赤茶色いレンガ造りで、入り口の上にはコンドリュー社の名前がレタリングされた看板が大きく掲げられている。その風貌は、ヘルメスの言っていた通り、街中でも特に目立っていた。
カンパニーを見上げていると、トン、と背中を小突かれた。
「顔、こわばってるところ悪いんだけど、俺はここで待ってるからな」
そっけなく口にしたヘルメスの言葉は、さて乗り込むぞと意気込んでいた僕の意欲をみるみる削いでいった。
「…え、え?待って、ヘルメス、僕、僕一人で行くの?」
情けないことに、てっきりヘルメスが仲介人のように何でもかんでもしてくれるつもりでいたので、突然ひとりきりになってしまったような不安に駆られる。
僕の動揺ぶりがあまりにも惨めであったのか、流石に悪びれた顔でヘルメスが言う。
「俺みたいのが一緒にいたら…その、な。ダメなんだ。この街じゃ、評判いいこと、してこなかったって言ったろ」
申し訳なさそうな顔で、僕の肩にポンと手を置いた。その手から、じわりと熱が伝わってくる。
僕は昨晩、森の中で交わした会話を思い出していた。彼がここ、セント・ロギオスから教会へ身を移したいきさつが、この街での窃盗からきているという話だ。詳しく聞くことができなかったけれど、町民から窃盗の罪で刑罰を受けそうになったところを、教父さまに救って頂いたと。その話を聞いた時の、心臓に流れた血の冷たさを思い出す。
「王都の修道院通いなんて立派な肩書きの奴が来てもさ、俺が隣にいたらな」
「カンパニーの人、ヘルメスのこと、知ってるの?」
「さてね。でもここは情報通の巣だぜ。顔はともかく、名前はほぼ確実に割れてるな。偽名使ってもいいけど、バレて信用問題にしたくない」
そう言うヘルメスの口元は笑っていた。でも同じ顔に浮かぶ竜胆色の瞳は今、薄寂しく寄る辺ない幼子のように憂いでいた。
「わが社に、ご用ですか」
不意に、脳天から滴るような声。
意識するよりも先に、体は震える。低く、優しく穏やかでありつつ、圧倒的な得も言えない不気味さ。
僕は、突然投げかけられたその声の方向を探って振り返った。
カンパニーの入り口で一人の男性がこちらを見て佇んでいる。
カンパニーの社員であろうか。眼鏡をかけたその男性は、柔和な笑みを浮かべて僕たちに会釈した。
僕らがコンドリュー・カンパニー社長室の応接ソファに座ることになるのに、それから数分とかからなかった。
*
カンパニー二階にある社長室は、こじんまりとしていた。実際は広めの間取りなのだけれど、新聞や大量の本がいたる場所に積まれていて足の踏み場はかなり少ない。そのせいで、せっかくの広い社長室はとても窮屈に感じる。
その散らばった情報の山を越えた先の窓辺には、まるで玉座のように大きなデスクが配置されている。席には、社長らしき人物はおろか、部屋には今、唖然とした僕とヘルメスがただ放置されているだけだ。
来客用らしいソファに腰を沈めて、僕は先ほど起こった出来事を思い出していた。
あの時。
声をかけてきた眼鏡の男性に僕らが何も言えないでいると、彼数秒こちらを眺めて、その後、思い出したように、おお、と素っ頓狂な声をあげた。
察した。気づいた。
そんな顔だった。
男性の合点がいく声を聞いて、横にいたヘルメスが小さく舌を鳴らした。
ヘルメスは、自分の窃盗犯としての素性を知られたと思ったのだろう、無表情のまま視線を落として「しくじった」と呟く。
男性の方は、何故だか嬉々として彼なりに状況を飲み込んでいるようで、何度も頷いていた。
そして、晴れ晴れとした、屈託のない透き通るような表情で指をパチンと鳴らした。
「我が社の門前で談義しておいでのようですが、立ち話もなんでしょう。中へお通しいたしますから、お茶でもどうですか」
僕らはきっと、同じ言葉を胸に抱えていたに違いなかった。
こいつは一体、何を言っているんだ?
ふと様子を伺うと、無表情を決め込んでいたヘルメスの顔にはついに、困惑と狼狽が浮かび上がっていた。なにせ、男性の提案するその魂胆が、さっぱりわからなかったからだ。
いや、わからないというわけではなかった。
むしろ、男性の腹積りを、僕らはやすやすと想像できてしまった。
今朝、ヘルメスにキャスケット帽を被せられた理由。
目の前の人の良さそうなこの男性がまさに、僕らの命を金に変えようとしているのではないか?
カンパニーの関係者が人身売買に手を染めているとは思いたくない。けれど、信じられる程の理由がどこにもない。そもそも、この男性はカンパニーの関係者ヅラをしているものの、実のところ全く無関係という可能性だってある。
たった数秒ほどの長い沈黙を、ヘルメスがやぶった。引きつった顔で無理やり笑顔をつくり「お気遣いだけで、どうも」と頭を下げる。
頭を垂れた瞬間、僕に視線を向けて、そっと「撤退だ」と囁いた。
なんていい判断だろうと感心した。僕は、男性からはわからない程度に小さく頷いた。とにかく一刻も早くこの場から離れたいほど、その男性は気味が悪かった。
踵を返そうとしたヘルメスに半歩遅れて、退散しようと振り返る。
そして、その瞬間、僕らはささやかにぞっとした。
僕らが男性から目を背けて振り向いたはずの先に、その男性は、いた。
まるで数秒前からそこで佇んでいたみたいに腕を組んで、気味悪さを極め付けるように、うっすらと笑った。
振り向いてみても、カンパニーの入り口によりかかっていたはずの男性の姿はもちろん、ない。
後頭部にぞわりと、男性の声が染み込んでくる。
「まあ、いいじゃないですか。どうぞご遠慮なさらず」
背中に冷たい汗がしたたっている。
一瞬の間に回り込まれた。と、言葉にすればシンプルなことなのに、目の前で起こったことは、どうしても奇術でしかなかった。
僕らは恐怖していた。この目の前の男性は、何がどうしてそんなにも僕らを引き止めるのだろう。
ヘルメスは、しばらく浅く呼吸をしてどう判断すべきかを考えているようだった。唾を飲み込む音が、やけに大きく聞こえた。
やがて、観念したように、大きく息を吐いた。「お言葉に、甘えます」と、今までで一番下手な作り笑いをする。
その返答を聞いて満足そうに手をあわせ、男性は、僕らをカンパニーの内部へ招き入れた。
数分前まで自ら乗り込む気でいた場所へ、まるで収容されるような気持ちで足を踏み入れることになるとは、思ってもいなかった。
*
社長室に通されてから、時計の長針はもうだいぶ傾いていた。
男性からここ社長室で待つように言われて、二人きり、この部屋で待ちぼうけをくらっている。
お互い緊張を通り越して、もう呆れたような顔になってソファに体を沈めていた。
「さっきの、なんだろ…あれ…」
僕が問うわけでもなく呟くと、ヘルメスは宙を仰いで、中指を立てた。
「さて、な。人間じゃないよ、あの動き。おまけに人をおちょくるみたいにヘラヘラしてて、気味悪いしさ」
ヘルメスは露骨に苛立ちながら、乱暴にソファから腰を上げた。床に散らばった新聞や本を器用に跨ぎながら、部屋を物色するように見て回っている。
「この後、ガタイのいい人が何人も来てさ。僕ら、どっかに連れてかれちゃったり、すると思う?」
自分で口にして、僕はその想像に気が遠くなる。腕の粟立ちをさすりながら、ソファの上で膝を抱え込んだ。
「ん…けども奴、どうも俺の方ばかりを見てる気がする。そりゃ、以前ここいらで悪さしてたガキって勘付いてんのかもしれないけど、それにしても、お前みたいな良い値がつきそうな子供を見て、目の色を変えようともしない」
僕は複雑な気持ちで聞いていた。目の色を変えられていても困るからだ。
歩みを止めないまま、ヘルメスは口元に手を当てて思索にふけっている。じっとしてはいられないようだった。
「別の思惑が、あの人にあるかもって?」
「…さあな」
そのまま、会話は途切れてしまった。
僕は僕で不安に飲まれないようにするのがやっとだったし、ヘルメスはきっと自分の言い出したことが原因で最悪の事態に至ってしまったら、と自分にむしゃくしゃしているのだ。
とても、のんびりと語らっていられる心境ではない。
「でも」
静けさを不器用に割って、ヘルメスが一呼吸置く。デスクの側で歩みを止めて、窓の外へ顔を向けた。わざとらしく、咳払いをする。
「何があっても最悪、お前は逃すよ」
こちらを見ずに、投げ捨てるようにそう言い放った。
部屋の外で、キシ、と板が鳴く。
あの男性が、戻ってきた。
とっさに身構えて、部屋のドアを凝視した。
この世の終わりのような音を立ててゆっくりと開かれた扉の先には、やはり先ほどの男性がその柔和な顔を覗かせていた。
いかにも人をとって食べてしまいそうな暴漢の姿などはなく、彼はひとりきりで社長室に足を踏み入れた。数人で力づく何かされるのではないとわかって、僕は小さく安堵する。
男性の手にしているものを見て、ぎょっとした。シルバートレイの上で輝く、美しい乳白色のティーセットだ。お茶でもどうぞ、という彼の言葉を思い出す。
「今じゃ嗜好品は手に入りませんからね。こんな茶葉しかないのですが、これでも貴重ですよ」
カチャカチャと陶器のこすれる音を立てながら、僕の目の前のテーブルにカップを置いた。
顔が一層近くなり、意識せずとも背筋がキュッと伸びる。
僕と男性の視線が、混じり合った。これだけ近くにいたら、仕方のないことだった。
僕が息を飲むのなんて気にもとめず、男性は柔らかに笑って見せた。
それから手馴れた様子で、ポットを手にした。優雅な手つきによって、ベリー色の液体がカップの中へ注がれていく。遠くの窓から太陽の光を受けて、白く湯気が煌めいた。
紅茶の香ばしさが、鼻先をかすめた。
男性は近くでよく見ると、人当たりのよい好青年という感じだ。年齢は三十手前ほどだろうか。薄茶色の細い髪と日焼けした肌が若々しくて、目元の丸メガネがいかにも記者らしい。
話し方もそうだったけれど、仕草や物腰は、丁寧で柔らかい。
ただ、それに勝る底知れない気味悪さを僕らは知っている。あの時の人間離れした動きと、そもそも意図の知れない数々の親切。
「そんな貴重なもんを、どうしてまた、俺らなんかに?」
テーブルとは離れた位置にあるデスクの側で、ヘルメスが挑戦的に言い放った。こちらを向いて、デスクに軽く腰をかけている。
男性はヘルメスに向き直る。何故だか嬉しそうな、誇らしげにも見える表情をしていた。
紅茶を注ぎ入れたティーカップをひとつ手にすると、ズンズンとヘルメスの元まで足を進めた。
一瞬ぎくりとしたヘルメスも、踏んばるように真正面から男性を見据えていた。
男性はヘルメスにティーカップを差し出すと、そのまま、おそらくたった一人しか座ることが許されないであろう立派な革張りの椅子に、我がもの顔で、どっかりと座り込んでしまった。
「まあどうぞ。まずはお召し上がりください。申し遅れましたが私はリゴット・コンドリュー。社長の名に恥じないほどには情報通ですからね。ヘルメス。あなたのこと、知っていますよ」
僕らは、思わず短く声をあげた。