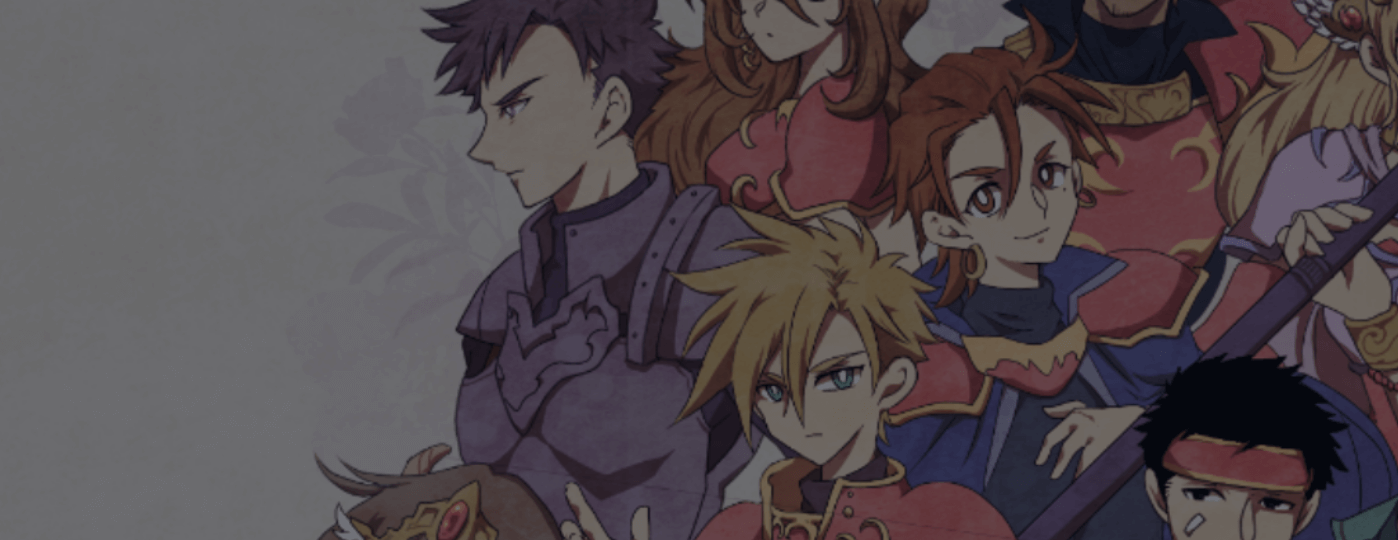3.帳の協定
僕がヘルメスの笑顔を初めて目にした頃には、外はもう濃いオレンジ色の夕空へと変化していた。柑橘類の香りが立ちこめそうな程色味の強い西日が、それでいてやわやわと、窓辺に差し込んでいた。
しばらくの間、僕らはその柔和な西日を浴びていた。
ヘルメスは僕にこの教会について教えてくれた。
ついさっき僕が歓迎を受けたこの部屋は、教会で生活する子供たちが寝床にしている。部屋には、家具と呼べるようなものはほとんどなく、ただ藁のマットレスだけが乱暴に転がっている。
藁をツタでくくって、使い古しの布で包んだような質素なものだ。つい、麻布や綿をつかったマットレスを敷いた、木のベッドが恋しくなってしまいそうになる。
藁のマットレスはだいたいどれも使い込まれた雑巾のようにぺちゃんこだったけれど、中には一つだけ、くたびれることもなくしっかり丁寧に作られたものがあった。
それは全部で、ぴったり六つ。僕の分も用意されいてた。
僕がここに来ることを知った誰かが、こしらえてくれたのだろう。ヘルメスに聞いてみると、彼はたじろいだように眉を寄せ、決まり悪そうにしていた。
その様子から、僕は想像してみた。
アルゴス達が僕のために健気に藁を積んでいるはずもなかったし、シスターの細い腕を思うと、きっと力仕事なんてしないだろう。
おそらく、今朝、僕がやってくることをシスターから直々に告げられたのはヘルメスで、彼はそれを断ることが出来なかったんじゃないか。
少し交わした会話からもわかるように、ヘルメスはとってもニヒリズムで、クールでいることに努めていたように感じる。とげとげしく愛想のない面立ちも、そういった印象をより強くしていたと思う。
ただそれでいて、不思議と頼り甲斐があった。
蹴りを食らって突っ伏していた僕の手を引いてくれた時の彼の、厄介そうに感じながらも放っておけない哀れみの表情を思うと、シスターがヘルメスを頼ってると考えても納得できた。
彼は損な役回りを引き寄せる体質なのかもしれなかった。よくよく見ると、やや大人びている横顔には、苦労の多さが刻まれている気がした。
ところでこの部屋にはその藁マットしか目立つものがなくて、僕が今まで勉強机にしていたような木箱とか、タンスみたいなものとか、身近に置いていた見慣れた必需品がこれといってなかった。
「念のために聞いておくんだけどさ、私物なんかはみんなどうしてるの」
「私物?なんだよ私物って」
ヘルメスは両の掌を宙にぴらぴらと浮かせながら、僕の足元に置かれたカバンを睨んだ。その眼差しは、どんなに大事なものがあるって?と言いたげだった。
彼のこざっぱりした身なりを見て、僕は何か悪いことをしたような気分になりながら、カバンを開いて見せた。
開ける瞬間、しまった。と、思った。
簡易ランプやマッチ、わずかな衣類。そんなものはどうでもよかった。
カバンには、修道院から持ってきた教科書と、筆とインクと羊皮紙が詰められているはずだった。
王都でも字の読み書きが出来る子供なんて少なかったのだから、よほど筋書きめいたことが起きない限り、ヘルメスもまた、そうであるはずだった。
自分と同じ年代の子供に読み書きの証を見せられて、いい気分なはずがない。少なくとも、手を叩いて喝采してくれるなんてことは、ないはずだ。
でもそんな考えがよぎった頃には、僕はすでにカバンの蓋を開いていた。
もちろん荷を作ったのは僕自身なので、想像通りのものがヘルメスの目に触れることとなった。
ヘルメスはその鋭い瞳をありったけに丸くして、僕の顔を覗き込んだ。
「字が?」
取り繕っても仕方がなかった。僕は素直に頷いた。
しばらくすると、ヘルメスはその猫のように丸くした瞳を、ゆっくりと細めて、相変わらずの無表情になった。そして、そうか、とつぶやいた。
「手癖の悪い奴が多いから、なくなるのが嫌ならそれは持ってた方が良いな」
僕は、自身の失態に対して、嫌味な奴だと非難されるのが相応しいと思っていた。だから、ヘルメスが皮肉すら口にしないことには、準備がなかった。
例えばこれがアルゴスに対して同じことをしていたら、たちまち僕は学力をひけらかしたことへの糾弾を受けただろう。
僕が考えすぎということはなかったはずだから、やっぱりヘルメスは見た目だけじゃなくて、中身も早熟していたのだと思う。
なんにしろ僕はこれ以上この話題を続けたくはなかったので、「そうだね」と言って話を切り上げた。
教科書やペンなんかは小銭程度であっても街では売値がつくだろうし、もしその価値がなくとも、アルゴス達に理由もなく隠されてしまうことだってあるだろう。なんせ僕は、彼らによほど好かれているようだったし。
僕はヘルメスの言うとおり、カバンは常に肩からかけていることにした。
「夜になる前に、行こう」
ヘルメスはそう言うと、部屋を出て、聖堂の方へ続く扉を開けた。どこへ行くのかと問うと、まあついて来い、とはぐらかされた。
僕らの部屋の他に生活圏は、シスターの個室と、井戸へ続く小さな厨房のみで、他には、この小さな聖堂があるだけだという。
こんな田舎の教会には、装飾が施された重厚な石造りの十字架や、色とりどりの美しいステンドグラスなんて、当然なかった。
そこにあったのは、慈悲なんて持ち合わせていそうにもない女神像だけだった。埃をかぶって蜘蛛の巣の張られた女神像は、燭台に灯されて、こじんまりと聖堂を見つめていた。
聖堂を歩いていると、丁度告解部屋から出てきたシスターと目が合った。
「あら!やっぱりあなたは、面倒見がいいのね」と、嬉しそうに目を細めて言ったのは、ヘルメスに向けた言葉だろう。ヘルメスは、愛想笑いをしてそそくさと聖堂を後にした。
外に出ると、空はすっかりと夜の準備を始めていた。
紫がかった雲のたなびく空は、ヘルメスの瞳のような色をたたえていた。
ヘルメスは「メシにしよう」と言って、何故かそのまま夜の道へと歩き出してしまった。
「ちょ、ちょっと待って。どこ行くのさ」
「メシだって、言ったろうよ」
とは言え、ヘルメスが歩みを進めようとしている方向は、どう見ても木々が立ち込める林、いや、森の入口だった。
「森の奥に、食堂があるの」
彼はやはり脚が長くて、僕が小走りでやっと隣に並ぶと、呆れたような顔で迎えられた。
「お前やっぱり、ちょいと変わってるよ」
僕は理由もわからぬまま貶されて納得がいかなかったけれど、ヘルメスはそんなことはお構いなしにどんどん森の方へと歩みを進めていった。
仕方なしに、僕は彼の後を追った。
木々のトンネルをくぐっていくと、空気の香りがだんだん青々としてきた。林のような小道は、すっかり傾斜のきつい山道になっていた。森の奥はどうも山へと続いているらしく、僕は内心ドキドキしていた。時折耳にする小動物の足音や鳴き声、木々のざわめきとか野鳥の羽音に、いちいちギョッとしてしまう。
しきりに、熊が出ないか、狼が集団で出たらどうしよう、と緊張していた僕を落ち着かせるつもりだったのか、ヘルメスは彼がここでどんな毎日を過ごしているのかを話し始めた。
最初は気もそぞろだった僕も、彼のくぐもっているのに透き通ったような不思議な声を聞いてるうちに、話に聞き入ってしまった。
そもそも、ヘルメスがここに身を置くようになったのは、数月前からのことだった。ここから一時間ほど歩いた辺りにあるセント・ロギオスという街での窃盗で罪に問われたところを、行きがかった教父さまに免罪をかけあってもらったことが経緯だったらしい。
窃盗と聞いて、僕はぎくりとした。
その行為自体への驚きもあったけれど、一般的には馴染みのない言葉を当然のように口にしていたことにも、狼狽えた。
僕はよほど動揺していたのか、ヘルメスにはそれが伝わってしまったようだった。気まずそうな顔をして「今は、してないよ」とぶっきらぼうに言った。その言葉の真意について、問い詰める気にはなれなかった。
ともかく、ヘルメスがここへ来たのは教父さまに連れられてのことだった。
教父さまがいらっしゃった頃、教会の支持は厚かったそうだ。
ここ一帯、裕福ではないものの、信仰心そのものが精神的な支えとなっている部分が強かったという。教父さまが聖書を朗読される時や讃歌を大勢で歌ったりする時なんて、多くの村人が訪れたみたいだ。
ここに預けられた子供たちは、教父さまと親しい近隣の村民から仕事をもらい、各々が稼いできた日銭や分けてもらった食料を持ち寄って、一般的にそうであるように、集団で生活していた。当番を決め、規律に則って、倫理的に生きていた。
けれども教父さま亡き後、教会は、どこからかやってきたあの若いシスターの独壇場になってしまった。人の希望の尊さを説くにはシスターは若すぎたし、彼女自身そんなに自分の役割を重く捉えてはいなかったようだった。
今では人々が礼拝することも珍しくなる程、村の信仰心は廃れてしまった。
もとより生活が厳しいこともあり、村民はわざわざ仕事を与えてくれることは極端に少なくなったという。
やがて、シスターがその有能な資金繰りの能力を発揮したのか、教父さまが残した資産も尽きようとしていた。
一日二食の食事の時間は朝の一度だけになった。
それも、かつては教父さまの部屋で食卓を囲っていたのが、今では無感情で事務的な配給のように、毎朝ただ硬くなった黒パンを受け取るだけとなってしまった。
今は国から教会へ献金があるものの、近い将来廃止となるだろう、とヘルメスは見越していた。
もちろん、そうとなれば身寄りのない子供なんて容赦なく追い出されてしまう。
ヘルメスだけではなく、他の子供達もそのことを察知し、彼らはみんな一人で生きられるように、適応する術を探すようになった。
ヘルメス以外の子供たちは徒党を組んだ。僅かでも集団が出来上がると、自ずと一人の中心人物が現れるように、その徒党はアルゴスをリーダーとして行動するようになった。
彼らはヘルメスにも集団に加わるように言ってきたけれど、ヘルメスは彼らと距離を置いた。集団で力の差がはっきりしてくると、分け前が均等のままであるはずは当然なかったし、ヘルメスは何より大勢で馴れ合うことを嫌っていた。
「差し伸べられた手を振り払ったら、お気に召さなかったようでね。善意を退けた報復を、ありったけもらったよ」
ヘルメスは拳を打ち込むようなそぶりをしながら言った。彼がリンチを食らったというのは、そういう経緯があったのだ。
「じゃあ、ヘルメス。キミは、ひとりでどうやって?」
ヘルメスは長い2本指を僕の目の前に差し出して、大事なことは二つだけだ、と言った。
まず第一に、食料の調達。
以前セント・ロギオスを拠点としていた頃は窃盗や日雇いで賄っていたヘルメスにとって、ここ一帯は未開の自然も多くて食料調達の面では格段に住みやすくなったらしい。
そのセント・ロギオスや王都にも続いている大きな川は、上流に行けば森の奥へ、更にその奥は木々が生い茂る山嶺へと至る。
ヘルメスはいつも、森の奥で魚やザリガニ、山菜や小動物を調達しているのだそうだ。今向かっている先が、まさにそうだ。彼がメシにしよう、と言ったのはこういうことだった。
次に大事なのが、仕事探しだ。
村で仕事を提供してくれる村民がいなくなってからは、まともな賃金を得るためには、セント・ロギオスまで繰り出すしかないようだった。
僕らのような子供でも出来る仕事は限られていて、運が悪ければ相手にされず、運が良ければわずかな報酬が得られる。そうして少しずつ貯めたお金で、生活に必要なものを調達するそうだ。
僕が今まで貴族の子供に紛れてペンを羊皮紙に走らせている間、ヘルメスはそうやって生きてきたのだと知った。
そんな話を聞かされながら、歩いて、十分ほど経った。
木が生い茂って緑の香りが強くなる。
更にここから五分ほど歩くと森の中心部になり、今日はその辺りに罠をはってるという。何が捕まってるかは、お楽しみだそうだ。
だんだん傾斜が急になり、僕は早くも音をあげそうになった。
けれども、ヘルメスの足取りは急斜を物ともせず軽く、僕が全身を使って這い上がっている横で、ガケのような傾斜をウサギのようにひょこひょこと登っていく。
そんな彼に遅れまいと無理をしたせいで、目的の場所に着く頃には僕の全身は汗だくで、ゼエゼエと肺で息をしていて、消耗の隠しようがなかった。
そんな僕を見て、ヘルメスは苦い顔をしていた。
「体力ないなあ」
「キ、キミと比べたら、誰だって、そうなんじゃない」
「休んどけ。ちょっと待ってなよ」
息切れしながら答えると、ヘルメスはそう言って川沿いを更に歩いて行った。
僕が川で喉の渇きを癒していると、十分も経たない内に、どこから持ってきたのか、小さな籠二つの中身を満たしてヘルメスは帰ってきた。
乱暴に置いた方の籠には乾燥した木の枝や枯れ草、少しばかりの木の実が詰まっていた。短時間でよくこんなに集められるね、と驚いていると、今日のメシは昨日のうちにめどをつけるもんだ、と言う。
もう一つの籠はヘルメスがやや得意そうに見せてくれた。
「え、ウグイ?」
籠には、ウグイが二匹と小さなカニが三匹入っている。よく見ると、ザリガニもいる。仕掛けた罠の精度の高さに感動していると、今度仕掛けの作り方を教えてやる、と言ってくれた。
ヘルメスは平らな岩を台にして、見慣れない形のナイフを取り出して手際よくウグイに処理を施していく。
「火は起こせるか?」
自身は魚を処理しながら、枯れ草や木の枝を顎で示した。
僕はカバンの中にマッチを入れていたのを思い出し、取り出した。
ヘルメスがウグイの内臓を取り出しながら、言うとおりにしてみ、と僕に指示を出してくれる。
枯れ草を一箇所に集めて拳ほどの石で囲い、空気の層を作る。その上に小さな枝、大きな枝の順番で重ねていく。一番柔らかそうな枯れ草の下にそっとマッチを差し込んで、ゆっくり火が広がっていくのを待っていると、やがて木の枝が赤く燃え上がった。
火柱が大きくなってくると、すっかり深い紺色の影で包まれていたあたりが、火のゆらめきに照らし出された。
ウグイを遠火にかけている間、僕たちはイチヂクやクルミで間をもたせた。
ヘルメスはウグイを処理したナイフを一振りして血を落とすと、丁寧に手入れを始める。乾いた葉を布のようにして魚の油をぬぐい取ってから、砥石のようなものを取り出して、錆を落としている。
僕はその様子を、少し楽しそうだと感じた。
「ねえ、そのナイフ。見たことないや。珍しいもの?」
ナイフは、真っ直ぐな片刃で、ところどころ錆ついているものの、刀身は腕の長さほどもある立派なものだ。鍔がないのが特長的で、柄の模様がどこか、異国めいている。黒光した鞘が、見たことのないような潤沢さで覆われていた。
「これな」
ヘルメスは刀身を鞘にしまうと、僕に差し出して見せてくれた。手にすると、ずっしりと重たい。軽々と扱える一般的なナイフとは、全く異なるものだというのがすぐにわかった。
「ここからずうっと東の国のものみたいだ。匕首っていうんだって」 「アイクチ?」
星がちくちくと浮かび始めた夜空に、ヘルメスは目を向けた。
まるで子供みたいな顔で、と言うと妙なんだけれど、今までで一番年齢に相応しい表情をして、その鋭い瞳いっぱいに星の光を浮かべていた。そこには、竜胆の花畑に星屑が流れ込んできたように、幻想的な瞬きがあった。
「俺さ、今よりは景気がずっとマシだった頃、武器職人のおっさんのとこで雑用やってたことがあるんだよ。異国の武器も結構な数、扱ってたかなあ。傭兵や王城兵士の御用達だったりして、いい店だったんだけど…」
話しかけて、ヘルメスはハッとした。 饒舌になっていたことに気づいたのか、少し気恥ずかしそうに咳払いをしてから、急に不自然なほど落ち着いて見せた。
「ま、そこで縁があって頂戴したんだよ」
それが何であれ、異国のもの、というだけで僕らのような子供は興味を惹かれるだろう。何せ、海を隔てた遠い地からやってきたものだ。
ヘルメスがいかに大人びてるとはいえ、そんな感覚が自分と同じなのだと知って僕は嬉しかった。
そして、あの、星の輝きで満ちた瞳が忘れられなかった。
物悲しさが見え隠れする彼の錆びかけた瞳を、夢のような星の輝きで溢れるほど煌かせて語るヘルメスが、僕はもっと見たいと思っていた。
しばらくすると、僕たちの間には沈黙が滞留していた。
木々がたまに唸りを上げる他には、薪が火の粉を巻き上げる音だけがパチパチと鳴っている。風のない静かな夜だ。
その反面で、僕の体の内側では全身をかけめぐるように大きな予感めいたものが、ざわついていた。ピリピリした空気というのは、肌ではなく体の中から感じるものなんだ。
沈殿した泥を掻き上げる水流や、腐敗した空気を凪ぐ大きな風のようなものが身体中を張っているのがわかった。
魚の焼ける香りが広がる。 火が通ったウグイを僕に差し出して、ヘルメスはこちらをまっすぐに見据えて、口を開いた。
「回りくどくなく言うよ。ココットさ、俺と、組んでくれないか」
その時、大きく焚き火がゆらめいて、ヘルメスの顔に写り込んだ。炎が宿ったヘルメスの瞳に囚われた時、僕の体の中で吹き荒れる風が、銀の矢のように胸を貫いた。
動悸を激しくさせながらもウグイにかぶりついて、僕は考えた。川魚独特の苦味が舌にしみる。
ここにきて数時間、僕はヘルメスの世話になりっぱなしだった。ヘルメスは、僕の何を見て、何を感じてこんな交渉を持ちかけているのだろうか。
「こんなこと自分で言うのも変だけど、僕が、何の役に立つと思ってそんなこと言うのさ?」
ヘルメスの顔を伺うと、彼は僕の肩にかけたカバンに目をやって「それだよ」とつぶやいた。
それ、で、僕は教会でのやりとりを思い出した。
ヘルメスが言うそれとは、カバンの中の教科書や筆やインクだ。つまり、僕の読み書きの知識のことを言っているのだった。
あの時、僕のカバンの中身をまじまじと見つめて瞳を丸くしていた彼の心中には、ひがみでも劣等感でもなく、ただ僕を自分の力として捉えようとする貪欲さがあったのだと知った。
僕は、何かと面倒を見てくれる理由に始めて合点がいった。
「写本とか、回覧書の仕事ってすごく割がいいんだ。他の仕事は、煙突掃除とかどぶさらいとか、正直進んでやりたいものじゃない。賃金だって少ないし…不衛生だから、病気のリスクだって高いから…だから、お前が、」
淡々とした口ぶりがだんだん勢いを失い、ヘルメスはそのまま口をつぐんだ。ここにきて初めて弱気そうな彼を見て、ひどく居たたまれない気持ちになる。
言い淀んでいる理由が、僕にはわかっていた。
僕がセント・ロギオスで仕事をするのであれば、代わりに、ヘルメスはきっと今夜のように食べ物を調達してくれたり、アルゴス達の好奇な悪意から守ってくれるだろう。そして、それを自分で提案しながらも、得た報酬を二分するには絶対的に割に合わないと彼は思っているに違いなかった。
字の読み書きが出来るというのは、そういうことだったのだ。
それでももちろん、そんなことは僕にとっては、全く気にならなかった。
逆に、僕は鼻の奥がツンとするくらいに胸がいっぱいだった。
狡猾に僕を誘い込むことが出来ずに口ごもってしまうような、そんな彼の見かけによらない、隠しようのない素直さにあてられて、僕は心臓が高鳴っているのを感じていた。
「…ヘルメスは、アルマムーンを知ってる?」
突然話題をそらしたことに、言うまでもなくヘルメスは面食らっていた。
それでも何か魂胆があるのだと思ってくれたようで、彼はひとつ首を縦に振った。
「あんなでかい国、新聞の読めない俺でも知ってるよ。魔物召喚術とか、ちょっと胡散臭い噂も聞くけどな」
「うん。今の王様が、ガーゴイルやグリフォンが住むって言い伝えのある島で、契約を交わしたってね。そんなの、嘘かもしれない。でもそれだけの力があるんだ。それでいて、平和主義を掲げてる。戦争を自分の代で終わらせようって言ってる」
アルマムーン現国王ダークフリードは、徹底して天下泰平を唱えていた。
一国の指導者としてあるべき姿ではあったけれども、その決意が尋常ではなかった。言い伝えの島に赴いたのは、側近だった親友を戦で失ってからという噂も流れてきている。
遠く離れたソロンに伝わるまでに脚色を経たとしても、僕はそれが本当ならいいな、と長い間思っていた。
「で、アルマムーンが、なんだって?」
ヘルメスにせっつかれて、今まで父にだって言ったことのない秘めた決意を、僕は初めて口にしようとしていた。
それは、僕が英雄譚を綴った物語が好きだった気持ちを告白するのと同じ事だった。
「行ってみたいんだ。争いのない世界を、作ろうとしている国。僕はアルマムーンに行きたい」
当然のようにヘルメスは失望にも似た、訝しい顔をしていた。
「…ずいぶん、夢見がちなことを言うな。もうちょい現実主義かと思ったけど」
深くため息をつかれても、僕はひるまなかった。射抜かれた銀の矢が、胸に未だ留まっているのを感じていた。
「ヘルメス。僕は、ペンタグラムは近いうちにレムリアにやられると思う。そうなればソロンみたいな力のない国なんて、ガス抜きでひどい目にあう」
僕が意図して今までにないくらい声を荒げると、ヘルメスは目の下をぴくりと引きつらせて険しい顔をした。そんな表情をすると、もうまるで大人そのもののようで、僕は気圧されそうになるのを堪えなきゃならなかった。
「長くないって言いたいのか。この国が」 「ヘルメスはさっきここに来るまでの間、あの教会が廃止されるのも秒読みだって言ってた。でも僕は、それよりもずっと早く、この国自体が滅びるんじゃないかって思ってる。きっと、猶予なんてないんだって」
確証はなかったけれど、戦争の話はいつだってそんなものだ。
父に聞いた話の中で、僕はペンタグラムの国王がソロン国民に徴兵を要請してきた時点で、違和感を覚えていた。
ペンタグラムは軍事力の高い国だったし、レムリアを迎え撃つにあたって、ウラノス将軍という剛勇な武将が隊を率いるのだそうだ。
それなのに、まともに実戦経験のないソロンの兵を引き連れる判断をした国王には、何か嫌な予感という名の不安がつきまとっていたのではないかと思えた。そして、そういう歴戦の指導者の悪い勘というのは、なぜか当たる事が多いのだった。
しばらくヘルメスは険しい顔していたけれど、それでもそれなりに、僕の言葉を噛み締めていた。
「ヘルメス、僕はキミと組むよ。組ませてほしい。僕の学力がお金になるってキミが教えてくれなきゃ、僕は知らなかった。それに罠の作り方だって知らないから、魚なんてきっと獲れない。キミがいなきゃ、今も腹の虫が鳴いてたんだから」
僕は意を決して、ヘルメスの懐に手を差し出した。
けれども、ヘルメスは意地悪そうな笑みをたたえて、首を横に振った。
「お前が言いたいことは、そうじゃないだろう」
「…そうだよ。これはその日暮らしの為の取引なんかじゃない、一大計画なんだよ。キミが組もうって言ってくれた時、決めていた。ヘルメスは、僕とアルマムーンに行くんだ」
言い終えた時には、僕は立ち上がっていた。
体全身が心臓になったような高揚感でいっぱいだった。今まで自分の本当の言葉をここまで誰かにさらけ出したことのなかった僕には、体や心が沸き立つのを抑える事が出来なかった。
気持ちを放出したことで頭が真っ白になっていた。
落ち着いてくると、僕はついさっきまで興奮状態にあったことがやや恥ずかしくなって、ヘルメスの顔を見ていられなくなった。
そんな様子がおかしかったのか、ヘルメスがくっくと声をあげて笑い、立ち上がった。
「お坊ちゃんみたいな顔立ちして、とんだ野心家だよ。リンチを食らっても、通りで肝が座ってるわけか」
そして、宙に浮かせたままの手のひらは、ようやく握り返された。