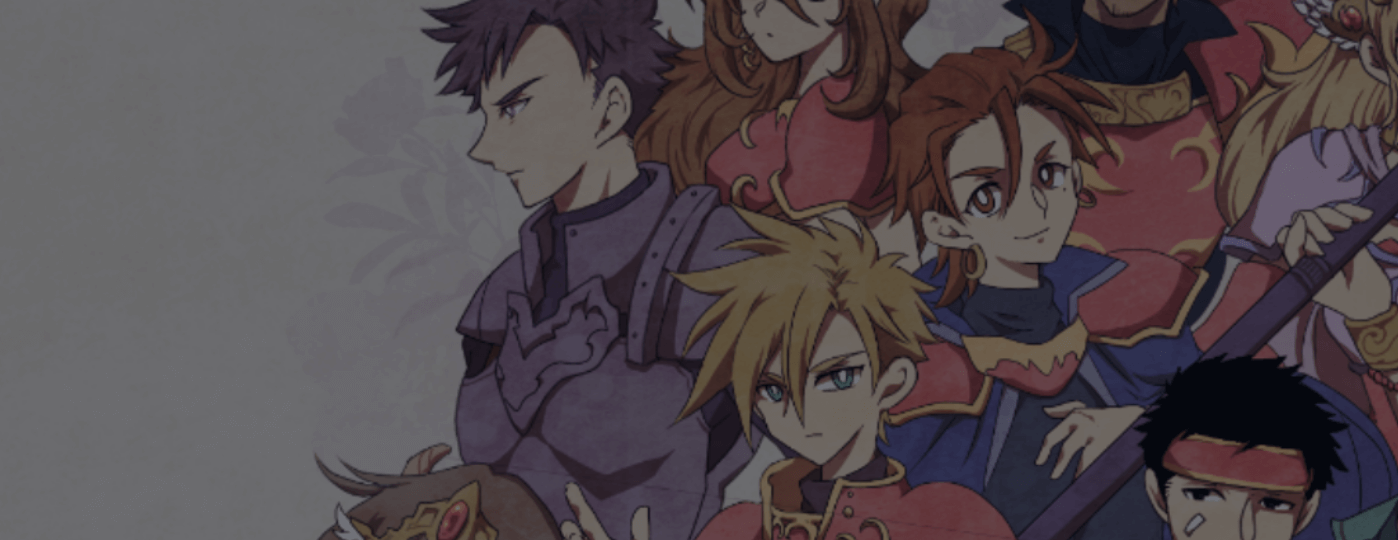5.本物のヒーロー
カンパニーの社長を名乗ったリゴット・コンドリュー氏は、スラックスに包まれた長い脚と、シャツから伸びる逞しい腕を大袈裟に組んでみせた。
カンパニーの一記者か、はたまた素性の知れない怪しい売人か。
僕らがそう訝っていた目の前の男性は、自らの正体こそがカンパニーの支柱であるとうそぶいた。
更にコンドリュー氏はヘルメスに、お前を知っている、と、まるで宣戦布告という名の銃口を突きつけるように向き直ったのだ。
ヘルメスは、立ち尽くしている。
地面を割って出たしなやかな茎のように長い脚を、震わすこともなく、床にしっかりと突き立てている。
動けないでいるのか、動じていないのか。
デスクから離れた、ソファに座ったままの僕からは、ヘルメスの今の心境を計り取ることは出来ない。
密やかな空間を渡っていくのは、時計の振り子が叩き出す規則的なリズムと、ティーカップから揺らめき立つ、白い柔らかな蒸気。
今や音を発し、動きを生じているのは、それだけだった。
窓枠に四角く切り取られた陽光が部屋の再奥から差し込んで、リゴット氏とヘルメスに仄暗い陰を落とす。
どちらかがため息混じりに、ふ、と笑みを漏らす。
ヘルメスだった。
「わざわざここまで連行してきたのは、今になって俺を弾劾する気になった。って、わけですか」
自棄になったようにして、ヘルメスはデスクの上のティーカップに口をつけた。紅茶はもうぬるくなってしまったのか、カップを覆して中身をあっという間に空にしてしまう。
飲み干したカップをやや乱暴に受け皿に叩きつけ、ヘルメスはリゴット氏を睨みつけた。
「はは、良い飲みっぷりだ。いかがですか。そこそこの茶葉でも、淹れ方ひとつでお客様にお出ししても、恥ずかしくないものになりますからね」
リゴット氏は意に介さないといった様子だ。
相変わらずの笑顔を向けた。
もちろんその対応に良い気がするわけもなく、ヘルメスは一層声に苛立ちを込めた。
「客?面白くない冗談だよ。この街で俺を知ってる奴が、とってつかまえて、糾弾するでもなく、もてなしてくれるってか」
もはや敬語なんて馬鹿馬鹿しくてつかっていられないと主張するように、ヘルメスはことさら乱暴に言ってのける。
今までの彼の喋り方を思い返してみると、穏やかであるか、冷ややかであった。
どちらにせよ、強い感情をあらわにするヘルメスというのを今まで知らなかったので、その声色の逼迫感に僕は目を見張った。
これ以上この場にいるのが息苦しいといった風で、もどかしそうな声だった。
自分でしかけておきながら見兼ねた様子で、リゴット氏は口角をあげて、眉を下げた。
「きちんとしたお客様ですよ、私にとっては。しかし、多少もったいぶりが過ぎましたかね。いや、失礼しました。きちんとお話しします」
リゴット氏は革張りの椅子に深く背を預けると、デスクの引き出しを開け、おもむろにあるものを取り出した。
デスク上に置かれた瞬間、重厚な音を立てたそれがあまりにも物騒なものであったから、僕らは息を飲んだ。
「それ…」
僕はつい、声を出していた。
それには、見覚えがあった。
正しくは、それに似たものを、昨晩ヘルメスに見せてもらったばかりだった。
僕は思わずソファから腰を上げ、デスク横で立ち尽くすヘルメスの側まで駆け寄った。
近くで見ると、間違いなかった。
昨夜、森で僕にウグイを捌いてくれたときの、異国製のナイフによく似ている。けれどもこれはナイフというより、その長さはもう剣だろう。
ひとしきりその剣を眺め終わり、僕は横目でヘルメスを盗み見る。
その顔は、やはり困惑で強張っている。
先程までの、焦燥感に駆られた落ち着きのなさは消えているものの、瞳がふるふると揺れ、おぼつかない。
「ヘルメス。これは、あなたのものなんです。私はずっと、あなたにこれを渡す使命を背負っていました」
リゴット氏は目を伏せて嚙みしめるように言った。
いよいよ、わけがわからなかった。
当のヘルメスにも全く覚えがなさそうだ。と、僕が思った矢先、ピンときたのか表情が急変した。
おそるおそるといった様子で腰のポケットに刺し込んでいた匕首を取り出す。
「これとは。…これとは、関係があるのか?」
リゴット氏の目の前に突き出した匕首を、ヘルメスはデスクの上にゆっくりと置いた。
並べてみると、それらはやはり同じ国から来た物だというのがわかる。
作りがよく似ているけれど、リゴット氏が取り出したものの方が長く、痛んでる様子もない。また、匕首にはなかった鍔には、複雑な模様が装飾されている。
リゴット氏は匕首に視線をこぼすと、微笑んで、ゆっくり頷いた。
「この街の武器職人のご老人から、最期の言葉をあずかっています」
その重々しいリゴット氏の言葉にようやく合点がいったようで、ヘルメスは口元に手を当てた。
眉根を寄せたその顔はみるみる青ざめ、唇に触れた指先は震えているようにも見えた。
「ヘルメス…大丈夫?」
そばにいる僕の存在すら忘れていたのか、ハッとして、こちらを振り返る。
暑くもないのにこめかみから頬を伝った汗は、きっと冷ややかであるに違いなかった。
細かに震えていた小さな紫の瞳は、僕を見て捉えると、ゆっくりと膨張していった。震えがとまって、かすかに安堵が浮かんだ。
「まさかお前に、心配されるとはな」
幾分ぶりかにヘルメスの不敵な笑みを見た。
僕には未だに理解できないものの、ヘルメスには少しずつ状況が紐解けてきたようだった。
大丈夫さ、と言って僕の背をポンポンと叩く。本来の彼自身を取り戻しつつあった。
お前に心配されるとは、なんていう彼の言葉は僕にはやや不服だったものの、その余裕のできた表情を見てほっとした。
「では、落ち着いたところで全容をお話ししましょうか。もちろんお友達にもわかるように。あ、お茶のおかわりを用意してからね」
✳︎
武器職人のご老人のもとで下働きをしていた頃のあなたは、まだ今よりずっと幼かった。
今から、二年は前でしょうかね。
あの鍛冶屋はここカンパニーからすぐの場所にありましたし、幼い子供がああいった危険物を取扱う店で働くのは珍しかったので、私はあなたのことを存じ上げていたんですよ。
あなたは店の裏側で雑用をこなすことが多かったため知らないでしょうけれども、私も護身程度には武器を嗜みますから、よく訪れていたのです。
店主のご老人とは、よく世間話ついでにお茶を飲んだりしていましたね。そう、こんな風に。
彼はご家族もいらっしゃらないようでしたし、身近な人間といえば、常連客か下働きのあなたでしたから、必然的にあなたの話ばかりしていました。
よく、坊主が、坊主が、ってね。
あなたが、とある異国の剣に興味を持ってることも、話してくれました。
国の名は、エブラーナ。
私には詳しいことは分かりませんが、この代物を目にしてもわかる通り、ここいらでは見かけない装飾と異様な気を宿した剣に、あなたは興味津々だったそうで。それがご老人には面白かったようですよ。
今思うと、あの店を継いでほしいと思っていたのかもしれませんね。
ご高齢でしたから。
ある時から体調をくずされて、そのまま…。
間に合わなくなる前に一度見舞いに行きました。
しかしその時、あなたは王都への納品のおつかいで、しばらく店を開けていたそうですね。
神は偏屈だったのでしょうかね。
間が悪かった。
あなたも、戻ってきた時は、さぞや驚かれたでしょう。
知っての通り、ご老人が亡くなった後の国の対応は早かった。店の品物は全て国が回収していきましたね。
すぐに別の職人が来て慌ただしくしていましたから、下働きの子供が…あなたがどうなったか、私が疑問に思う頃にはあなたの行方は分からなくなっていた。
こんな後になって今更言うのもいやらしいですが、店主が他界してしまってからあなたがどうしていたのか、気になっていたんですよ。
それから、随分と経ちました。
もうそのことが頭をよぎらなくなった頃かな、私宛に届いた荷物がありました。まあ、それがこれ。だったんですけどね。
脇差、というものだそうです。
添えてあった手紙は、これをあなたに渡してほしいという内容でした。あの店で一番の業物だそうです。
名もきちんと伝えるように…と言われていたのですが。
ええと、そう、ソウ…ダノ、ミツエ。双蛇御杖。
私、物覚えは良い方なのですが、どうもこれは何度復唱しても馴染まない呼び名ですよね。
名の由来はエブラーナの言葉で、争いあう二匹の蛇神を仲裁した…とかいう逸話からきている名刀だそうです。
ここでは国の許可なく武器は所持出来ませんから、既にあなたに手渡されているその匕首というのは、ほとんど使い物にならない廃材扱いということになっています。
ただ、一見してわかるように、これは違う。
ご自身の命がわずかであることを悟る前から、こうなるように手筈を踏んでいたようです。
国に回収されないように存在すら隠して、その日限りの何でも屋を雇って、更に幾月もはさんで私を介してまで、あなたに届けようとしていた。
今じゃ私も立派な不法所持者ですよ、カンパニー社長とあろう者がね。
そこまでされてやり遂げないわけにもいかず…随分探したのですが、あなたは中々にすばしっこいネズミのようで。
手がかりを得てもすぐに身を隠してしまう。
そりゃあ、窃盗なんかしていたら必要以上にコソコソするようになりますよね。あ、いやあ、糾弾しようとしているわけではなく…。
私はあなたがどんな罪を重ねていても、それはどうでもよかったんです。うちに被害はありませんでしたしね。はは、冗談ですけれども。
ただこの、命を継いだ届け物は果たさなければならないと感じていた。
あなたが教会に身をやつしていると知ったのは、本当に、つい最近のことでした。
訪れようと思っていた矢先に、現れたのは本日、あなたの方からだった。
先程あなたを見かけて、成長ぶりに別人かとも思いました。
でも腰に差したその代物を見て、やっぱり合点がいきましたよ。
逃すまいと、つい、少しだけ躍起になってしまいました。
私があなた方を捕らえようとしているとお思いになったでしょう?はは、脅かしてしまってすみませんでした。お友達も、ね。
そういうわけです。ヘルメス、キミにこれを捧げます。
幸か不幸か、戦時中ということもある。国の監視は厳しくない。
今なら隠し持つことも出来ましょう。
ご老人の命をどうぞ、継いでください。
✳︎
リゴット氏は僕らをソファに座らせ、部屋を徘徊するように、おもむろに歩みを進めながら静かに語ってくれた。
時折、床に散らばる書物に足を引っ掛けて慌てたりする様には、先程の俊敏な動きを見せた時のあの不気味さは微塵もなかった。
彼の素性を知って、また感慨深い話を聞かされ、僕はすっかり心の平静を保てるようになっていた。
おそるおそるといった様子で、ヘルメスは手渡された脇差の鞘を少しだけ引き抜いた。
反射で、虹彩が縮み上がる。
目が眩むほどまばゆいその煌きは、朝の光に反射する川の水面のようだ。
研ぎ澄まされた刃の上を、波打って渡っていく波紋がとても美しい。隣にいた僕でさえ目を奪われていたのだから、渡された当の本人の瞳に写り込んだ光は、その手元の刃に負けないくらいに瞬いていた。
「こんな代物もらっちまってもなぁ。教会には置いとけないし、使えないもの持ってても仕方ないよ」
口にしたその言葉とは裏腹に、厄介そうな顔どころか、まるで同い年の少年のような(と表現するのは変なのだけれど)顔をしていた。ヘルメスは、このエブラーナという国の剣の持つ、独特な様相を相当気に入っているのだ。ウットリとした表情にすらなって、心を奪われていた。
話の折り合いがついたことで張り詰めていた空気が緩んだというのに、僕はなんだか気がそぞろになってきてしまう。
リゴット社長の得体の知れない執着の理由がヘルメスにあると知って、すっかり脇役気分でいた。
けれど僕らの本来の目的としては、僕こそが主立って社長と掛け合わなければならなかったのだ。
偶然とはいえヘルメスの繋いだ縁のおかげで、お膳立てとしてはこれ以上ない程に完璧だった。
「あの、社長さん。何から話したら良いのか…えっと、僕はココットと言います」
僕が社長に向き直ったことでヘルメスも本来の目的に気が向いたのか、脇差をソファに置いて僕の背に立つ。
「リゴットでいいですよ、ココット。はじめまして。そういえば、あなた方何故にこちらにおいでになったのですか?ここいらに用事が?」
リゴットさんもいつ僕が話しかけてくるのかを待っていたかのように、こちらを見て微笑んだ。
思いがけないヘルメスの身の上話を聞くことになったついでと思い、僕はここに来る経緯の全てを話すことにした。
僕が口どもりながらも話す間、リゴットさんは三回も紅茶を淹れてくれたのだった。
✳︎
暗くなる前、薄く棚引く雲の際が金色に輝きだす頃に、僕らはセント・ロギオスの街を出た。
夜のセント・ロギオスは特に危険だ。
ヘルメスもリゴットさんも声をそろえてそう言うので、大通りになけなしの人気がある内に教会へ戻ることにした。
鍛冶屋の主人から託された脇差、双蛇御杖は、今ヘルメスの腰には携えられてはいない。
教会にあの脇差を持っていけば、たちまちアルゴスたちの餌食になるだろう。もしくはシスターに、あの偏った正義感のもと没収されるのはもっとつまらないかもしれない。
しばらくの間、脇差はカンパニーに置かせてもらうことになった。
明日から、僕らはこのセント・ロギオスの街へ通うこととなった。
結論から言うと、リゴットさんは、突然のことにも関わらず僕らの要求を二つ返事でのんでくれたのだ。
その上、僕とヘルメスの双方ともカンパニーで世話してくれるという提案をしてくれた時には、あまりの都合の良さにたじろいだ。
「いいですとも、あなた方、明日から毎日ここへおいでなさい」
なんて、にこやかに、おっとりと首を揺らしたものだから、一大決心していた僕はその拍子で力が抜けてしまった。
「人の形見だというのになかなかお渡し出来ませんでしたから、その罪滅ぼし、いえ、延滞料金の代わりと言ってはなんですが。それに、就職先に我が社の門を叩くなんて、先見の明がある有望な若者たちを放っておくわけにもまいりません。キミらにはできるだけの便宜を図らせてください。と言っても、我が社に勤めるからにはコキ使わせていただきますけれどもね」
僕らがあまりにも腑に落ちない顔でいるものだから、リゴットさんは付け足すようにそう話してくれた。
この時勢にここまで献身的な考えの人間がいるのだろうか。僕にはなんとなく納得出来ないでいたけれども、ヘルメスにはそれ以上に別のことで頭がいっぱいだったようだ。眉を寄せて、自分に出来ることなんてあるのか、とリゴットさんに不安の声を漏らす。
「あなた方にはそれぞれ別の部隊で働いてもらうことにしましょう。まず、ココット。キミは勉学が達者だそうですから、このカンパニー本部で雑…、いや、私がオールマイティな一流の記者に仕立ててあげましょう。ヘルメス、あなたは別働隊に所属してもらう。うちでは別の町からの情報の吸い上げ、手紙の配達もやってます。体力勝負の仕事ですから、あなたにはぴったりでしょう」
体力勝負、と聞いて、ヘルメスはあからさまに安堵の顔になって、ため息をつく。僕にしてみれば、そちらの方が重苦しい任務でしかない。そういう意味では、リゴットさんには僕らの得手不得手がわかっていたのだ。人の適正を瞬時に見抜く事が出来るあたり、社長でこその手腕なのだろうか。
カンパニーから出た僕らは、落ち着きがなかった。
ヘルメスには思いがけない出会いがあったことで、僕の方はヘルメスの境遇を知ったことで、それぞれ無言で考え込むこともあった。
武器職人のもとで下働きをしていた頃のヘルメスや、そこを追われて生きるために窃盗をするしかなかったヘルメス。リゴットさんの口から語られたヘルメスを、僕はまだ別の人間の話のように聞くことしかできなかった。
この短い間でも、僕は彼のことをもっと知りたいと、出来ればこの目で見て彼を感じたいという気持ちが強くなっていた。
街の大通りに通ずる外への大橋まで来ると、橋下を流れていくせせらぎがザアザアと聞こえてくる。
ゆっくりと歩みを進めていたヘルメスが、長い脚を少しずつ遅めて、川下を眺めるように遠くを見た。
「ココット。ちょっと」
ヘルメスは思いついたように声をかけ、僕の袖を引いた。
そのまま小走りに橋の中央まで来ると、石造りの手すりによっと腰掛ける。僕も隣へ座るように促す。
手すりの縁をのぞくと、水流の激しい川がしぶきをあげているのが見えた。川面は夕日のくっきりとした光のシルエットを浮かべて、トパーズのような煌めきを放っている。思わず、目を細めて光の粒を滲ませる。
ヘルメスは振り返って、川の流れて行く先を親指で差した。
「この下流のむこう。ずーっと行くと、レテ川っていうでっかい川に合流するんだ。レテ川の先に何があるか、ココットなら知ってるよな」
ヘルメスは一本指を立てて、まるで先導者のような手振りで僕に話を振った。
レテ川。
その川の名前は、僕の頭にピリリと小さな雷を落とした。
父とよく読んでいた国立新聞の隅。
そこには簡略化して描かれた、小さな大陸地図がのっていた。
僕はそれを切り取って、大事に教科書に挟んでいた。その教科書は今、僕の肩から下がっているカバンに入れているはずだ。
僕は少し慌ただしい気持ちになりながら、カバンの中を探り、その紙片取り出して広げた。
小さな地図の上のレテ川が流れる先には、頭で思い描いていた国へと、やはり繋がっていた。
僕は叫ぶようにヘルメスに振り返った。
「ベール国だ、ベール国。ヘルメス!」
紙片の上の小さなレテ川を指差して言う。
ヘルメスは目を閉じて、満足そうに頷いた。彼には、僕が芳しい顔をするのがわかっていたのだ。
瞼は伏せていても、あの竜胆色の瞳にはきっと、優しい光が宿っていた。
ベール国。
天然資源が豊かなことで知られている小国だ。
鉱山をひとつ抱えているほか、森林の整備に鳥獣の保護、水質の改善を分野にしている大きな研究所がある。
その豊かな資源とそれをいかに持続させるかのノウハウが、支配欲にまみれた国の侵犯から今まで守られてきたのには、理由があった。
それこそ、僕らが今夢みている大国アルマムーンの幇助によるものだ。
ベール国は王政ではなく、区画ごとに領主がその土地を治めている。
詳しい繋がりは僕にしてみれば不明瞭だけれど、領主はみんな、かつてアルマムーンの王家に仕えていた家系だそうだ。
このことは、ベールはアルマムーンの一部であることを意味しているといってもよかった。
この川の流れを遙かに下っていけば、やがては夢のたもとにたどり着く事ができるのだ。
ヘルメスは暗に、そう言いたいのだった。
「川沿いだと道も整備されているだろうし、小さくとも集落くらいあるだろう。まだ先のことだけどさ、もしかしたらここが俺たちの出発点になるのかも。…なんてな」
ヘルメスは、橋の手すりから腰を下ろして、少しずつ見せるようになってきた貴重な笑顔を作った。そして、すぐに気恥ずかしくなったのか、視線を川面に落としてしまう。
心臓の壁に、血流がドッと乱暴に打ちつけられる。
僕は縮み上がるように、身が強張ったのを感じた。
まだ見ぬベール国の情景を想って胸を高鳴らせたわけではない。ヘルメスといると、時々こんな、居ても立っても居られない気持ちになってしまう。
決して敵わないという強い劣等感と、自身もこうなりたいという確固な憧れの交錯。
そうだ、これは僕が長らく夢見ていた、あれに対する気持ちだったのだ。
「…ヘルメス、今日のこともそうだけれど、僕が言い出したことなのに、全部キミに任せちゃってるね」
言葉にすると、思いがこみ上げて、声が潤むのを堪えるのがやっとだった。
川のしぶきがやけに大きく聞こえるのに、ヘルメスの小さな喫驚の吐息を聞き漏らすことはなかった。
でも僕。いまに、絶対に力になってみせるよ。
今はまだ、この言葉すら飲み込んでしまうけれど。
ヘルメスはいたたまれないような、決まりの悪い顔をして、僕から目をそらした。人から賛辞を受けたり期待や感謝を向けられたりすると、ヘルメスは決まってこうだった。
「そういう話は、全部終わってからするもんだろ」
何でもない風を装った声は、居心地悪そうに向けた背中越しに聞こえた。
幼い頃から読みふけっていた英雄譚を綴った物語の主人公。
それは剛毅で正直で、朗らかに笑う快活な人物なのだろうと想像していた。
でも、本物のヒーローは、案外そうではないのかもしれない。
今、僕の行く先に導きの火を灯すのは、寡黙で皮肉屋で、器用なのに不器用で。
それでもきちんと僕の手を引いてくれる、刀好きの少年なのだから。